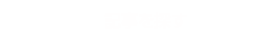皆さんは、「ために生きる実践」として、どんなことを継続して行っていますか?
私は、大学生の頃から献血をするようになって、今週日曜日、最寄りの献血センターで157回目を迎えました。
日本には、1000回を超えて表彰されている方もいるので、まだまだ誇れる数ではありませんが、〝少しでも人の役に立ちたい〟と思い、コツコツと続けてきました。

とは言うものの、献血をするようになったきっかけは、自慢できるものではありません。それは、30年ほど前にさかのぼります。
学生時代、寮に住んでいた私は、ある日、先輩から、「お菓子の食べ放題に連れていってあげるよ」と言われました。先輩がおごってくれるのかと思いきや、その行き先が、献血センターだったのです。
テーブルに置かれたバスケットには、お菓子が山盛りになり、飲料の自動販売機は、お金を入れていないにもかかわらず、全てのランプが点灯していました。私は思わず、「えっ!」と声を上げてしまいました。
寮で生活していた頃は、本当におなかが、すいていたのでしょう。恥ずかしいことですが、お菓子を目当てに献血に行っていたというところがありました。
実は、他の先輩に、「疲れているね。じゃあ、おいしいものでも食べにいこうか!」と言われて、ついていくと、デパ地下の試食コーナーだったということもありました。懐かしい笑い話です。

その後、私は、東北、九州、関東で献身的に歩み、その赴任先でも献血をしに行きました。地域によって医師や看護師の雰囲気や言葉のイントネーションは変わりましたが、どこに行っても、人の温かさが伝わってくるのは、同じでした。
私の次女(16歳)は、小さい頃に体が弱く、生まれた直後も含めて、7度、肺炎で入院しました。そのつど、24時間体制で医師や看護師のお世話になっています。また、小児ぜんそくのため、小学校4年生まで、毎月1回、通院していました。
両親は、三重県の実家で元気に暮らしていますが、父は前立腺がんを患い、放射線治療を受けました。母は不整脈が原因で心臓にペースメーカーを入れています。
そのようにして、家族が日本の医療に助けられたこともあり、今では、恩返しの気持ちもあって、献血に通っています。
近年は、少子高齢化の影響で、献血ができる人口(16〜69歳)が減り、さらに、10代から30代の献血者数は、この10年で約25%(2014年度:約215万人〜2023年度:約162万人)も減少したそうです。(出典:「政府広報オンライン」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/3.html)
この前、長男(19歳)に、「献血、一緒に行かない?」と誘うと、「行くわけないじゃん。血あげるとか意味分かんないし」と言われました。長女(17歳)からは、「絶対に無理。受験生に時間はないしね」と断られました。
〝伝道〟は、やっぱり難しいですね。

あるとき、鼻炎の治療を続けている次女に、「小さい頃から病院にお世話になってきたし、医療従事者になったらどうかな?」と話しかけると、「うーん。理系無理。数学、全然分かんない」と拒否されました。
今のところ、ドラマや映画で見るように、「お世話になったお医者さんのようになりたい!」と、勉学に励むということは、なさそうです。
私たちは、真の父母様から「愛天・愛人・愛国」の思想が与えられました。その教えを、どのような形で表していくかは、各自に与えられた個性や環境によって違うのだろうと思います。
子供たちが、「自分は、これで社会に貢献していくんだ!」と、自信を持って言えるものを見つけられるように願っています。
そして私自身も、ために生きる実体を目指して、努力を続けていきたいです。