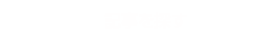【韓国昔話40】沈清伝2「お乳とご飯を恵んでもらう生活」
妻を失った沈盲人の悲しみは、言葉では言い表せませんでした。
村の人々の助けで葬式を行ったのち、沈盲人は、世の中がこれ以上ないほど寂しく、不安に思われました。
沈盲人は、妻のあとについてあの世に行きたいと思いました。しかし、幼い娘を残して死ぬことはできませんでした。
「子よ、泣くな。おまえの母は、もう遠い所に行ってしまったのだ。どんなに泣いたところで、飲ませてあげられるお乳はひと口もないのだ」
沈盲人は、泣く赤ん坊をあやしながら、自分も一緒に泣きました。
赤ん坊は、おなかがすいたとむずがっているようすでした。しかし、赤ん坊に飲ませるお乳がどこにあるでしょうか。
沈盲人は、手探りして台所に行って、一杯の器に水をくんできました。水を指につけて赤ん坊の口にくわえさせると、赤ん坊は、それをお乳だと思ってちゅっちゅっと吸いました。
しかし、水のついた指をいくら吸っても、おなかはいっぱいになりません。赤ん坊は、再びおぎゃあおぎゃあと悲しそうに泣きました。
泣いてむずがる赤ん坊をあやしたりなだめたりしながら夜を明かした沈盲人は、朝になって鳥たちがさえずりはじめると、赤ん坊を抱いて、杖で道をさがしながらお乳をもらいに出掛けました。
沈盲人は、妻が生きていたときに一番親しかった裏の村の貴徳母さんを訪ねていきました。
「おなかが空いたとむずがるうちの清に、お乳を少し分けてくれませんか」
「本当に、目の見えない父親に母親のいない赤ん坊とはかわいそうなことだ‥‥。さあ、お入りください」
貴徳母さんは、二人を家の中に招き入れ、赤ん坊にはお乳を与え、沈盲人には朝ご飯を出してあげました。
そればかりではありません。貴徳母さんは、乳飲み子をもった母親たちをさがしてまわり、このように頼みました。
「沈盲人の幼い娘に、お乳を少しずつ分けて飲ませてあげましょう。かわいそうな二人の面倒を見てあげれば、きっと仏様がよい報いを与えてくださるでしょう」
「かわいそうな隣人を見て見ぬふりはできませんよ」
「お乳も分けてあげ、沈盲人にも、ときどき食事を出してあげますよ」
だれもが同情し助けてくれたので、沈盲人はどうにかこうにか娘を育てていけるようになりました。
沈盲人は、夜が明けると、あの家この家にお乳をもらいにまわるようになりました。ときには川で洗濯をしているお母さんたちからお乳をもらい、ときには田んぼや畑で仕事をしているお母さんたちからもお乳をもらいました。
幸い、清は、病気一つせずにすくすくと育ちました。父親の前でのかわいらしいしぐさも増えました。
「わたし、おしっこしたい」
このように、言葉も上手に学んでいきました。
清が歩けるようになると、沈盲人の苦労はだいぶ減っていきました。清が沈盲人の杖の端を握り、先に立って道を案内してあげたからです。
杖の端を握ってちょこちょこ歩いていく清と、もう片方の端をつかんでたどたどしくついていく沈盲人の姿を見て、人々は、
「娘は暮らしの元手と言うが、沈盲人は、もう娘の恩恵にあずかっている」
と言って、冷やかし半分、うらやましさ半分で冗談をかけました。
すると、沈盲人は、見えない目をぱちくりさせながら
「ほっほっ、あなたがたも、生きていれば子供の恩恵にあずかる日があるでしょう」
と、うまくとぼけてかわしました。
いずれにしても、娘の手に引かれて歩くようになると、沈盲人の物ごいは、以前よりもはるかに楽になりました。
この家あの家でひと握りずつ与えてくれるご飯をひさごに入れて帰ってくると、沈盲人は、娘と向かい合って、もらったご飯を仲むつまじく食べました。
ときには昔の冗談好きがよみがえり、娘を笑わせたりもしました。
「清よ、わが家はきのうも正月の十五日で、きょうも正月の十五日だなあ、ほっほっほっ」
「お父さん、それはどういう意味?」
「米のご飯に、麦ご飯、豆ご飯、小豆ご飯、トウモロコシご飯まで混ざったご飯なので、正月の十五日に食べる五穀飯ではないか」
「ほんとだ」
清も、からからと笑いました。
韓国には、正月の十五日に五穀飯を炊いて食べる風習があります。沈盲人は、さまざまな雑穀が混じったご飯を「正月十五日の五穀飯だ」と言ってとぼけたのです。
しかし、清が六歳になったある日、床から起き上がった沈盲人は、はあっとため息をついて嘆きました。
「ああ、なんという運命だ。このように長い年月、あの家この家で物ごいをしてまわるとは‥‥。春になったのに花が咲いている景色を見ることができるだろうか、鳥が飛んでいるようすを見ることができるだろうか‥‥。ああ、なんというわたしの運命だ」
沈盲人は、物ごいに出掛けることにうんざりしてしまったのです。
やるせない声でつぶやいている父をくりくりした瞳で見つめていた清が言いました。
「お父さん、きょうからは、わたし一人でご飯をもらいにまわるので、お父さんは家にいてください」
「そうすることはできない。一緒に出かけよう」
「いいえ。わたし一人で行きます」
清はそのように言い張り、一人でご飯をもらうために出かけていきました。
「あれっ、きょうはどうして一人で来たのかね?」
村の人々が尋ねると、清はしらばくれてこう答えました。
「お父さんの体の具合がよくないのです」
「まったく、かわいそうなことだ。幼いのに本当に苦労が多いねえ」
人々は、清が持っているひさごにご飯とおかずをたっぷり入れてくれました。
この時から、清は、父親を家に置いて一人でご飯をもらいにまわるようになりました。
このような苦労の中でも、沈清はすくすくと育ち、十五歳になりました。
ある日、沈清は、向かいの村の武陵村で一人暮らしをしている婦人の家にご飯をもらいに行きました。
婦人は、大臣までつとめた夫を亡くし、武陵村に来て一人で暮らしている人でした。人々は、婦人の家を指して「大臣のお宅」と呼んでいました。
ちょうどこの日は、大臣のお宅の婦人の誕生日でした。
「清か、よく来たね! きょうは人手が足りないので、台所仕事を少し手伝ってくれないか」
「はい、お手伝いします」
沈清は、遅くまで大臣のお宅で台所仕事を手伝いました。
つづく