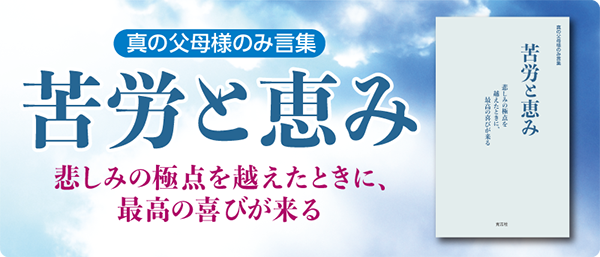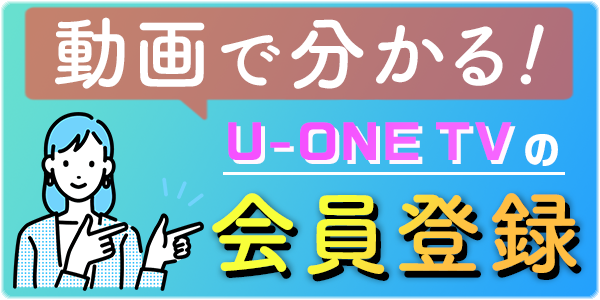「宗教」を読み解く 377
公生涯を歩むイエスと母マリア
2025.08.19 17:00

シリーズ・「宗教」を読み解く 377
ユダヤ・キリスト教の歴史に見る母なる者の使命⑨
公生涯を歩むイエスと母マリア
ナビゲーター:石丸 志信
四つの福音書は、ナザレのイエスこそが神の独り子、メシヤ=キリストであると証言するもので、新約聖書の中でも特別な位置を占めている。
ただ、その中で語られるのは、「公生涯」のわずかな期間の出来事に終始しており、野を彷徨(ほうこう)する哀れな説教者のごときイエスの姿しか描きだしていない。
かつてみ使いがマリアに告げた。
「その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない」(ルカによる福音書 第1章32~33節、新共同訳)
その栄光の王の姿は見る影もない。事もあろうに、その生涯は最も悲惨な十字架の死で終わるのだが、「神に呪われたもの」(申命記 第21章23節、新共同訳)のごとくユダヤの民からは忌み嫌われるべき出来事を隠すことなく、あからさまに告げている。
イエスの弟子たちの経験したことが、十字架を担って逝かれたかたが復活した後に、裏切った者を赦(ゆる)し愛して、さらには聖霊によって生まれ変わらせてくださったことだったが故に、このかたこそ神の子であると堂々と証言するようになった。
それ故、十字架の道も避けることのできない道であったと受け止めるしかなかった。
「悔い改めよ。天の国は近づいた」(マタイによる福音書 第4章17節、新共同訳)と言って宣教を開始したイエスに突然召された者たちは、律法学者のように深い教養があったとは言い難い。
それ故、彼らにとってイエスがいかなるかたかを理解するのは容易ではなかっただろう。
では、母マリアはどうだろうか。彼の親族はどうだっただろうか。
少なくともマリアは、イエスはどのようなかたであるかを知らされ、それを受け止めたはずであった。
ところが、宣教に明け暮れるイエスを気遣う様子は見られない。
み使いのお告げの内容やイエス誕生の出来事を深く心に留めて、静かに見守るだけだったのだろうか。
共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ)には次のようなエピソードが記されている。
「イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた」(マルコによる福音書 第3章31節)
母兄弟が来たとの知らせにイエスはこう答える。
「わたしの母、わたしの兄弟とはだれか」「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。神の御心(みこころ)を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ」(同福音書 第3章33~35節、新共同訳)
イエスに群がる群衆にとってはありがたい教えだが、母兄弟にはどう聞こえただろうか。
彼らがこのメッセージを聞いて心打たれ、イエスと共に行動し支えるようになったわけではない。彼らがイエスを理解していたとは思えない。
そんな家族から離れ、貧しき者たちの前で神の国の福音を伝える孤独な姿しか見えてこないのだ。
★おすすめ関連動画★
ザ・インタビュー 第22回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その1)「超宗教運動の30年を振り返って」】
ザ・インタビュー 第23回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その2)「宗教者の対話を促進する『超宗教フォーラム』」】
ザ・インタビュー 第24回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その3)「宗教者の役割と祈りの重要性」】
ザ・インタビュー 第25回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その4)「超宗教平和運動への召命」】
---
U-ONE TVの動画を見るにはU-ONE TVアプリが必要です!
無料ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードはコチラから