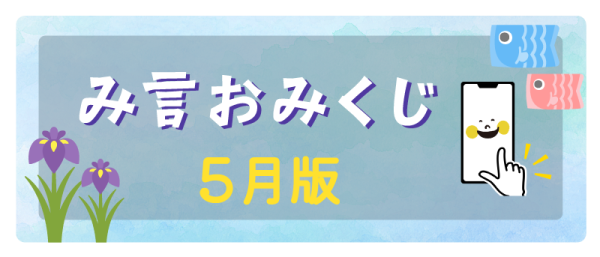青少年事情と教育を考える 295
「宗教を持つ人が身近にいる」という教育
2025.06.20 17:00

青少年事情と教育を考える 295
「宗教を持つ人が身近にいる」という教育
ナビゲーター:中田 孝誠
最近、宗教関係者の間で話題になっていることの一つに、日本に滞在する在留外国人の増加があります。
在留外国人は昨年末で約377万人です。中国や韓国、ベトナム、フィリピン、ネパールなどの国々から来ている人が多いわけですが、何らかの信仰を持っている人が大勢います。
異国で暮らす場合、自身が信じる宗教の施設、コミュニティーが、大切な心の支えになりますし、交流の場になります。
また、従来から文化の違いによる地域住民との摩擦が問題となってきました。文化の根本になっているのは宗教です。最近では、イスラム教の土葬を巡って摩擦が起きている地域があります。
そこで現実には、おのおのの人の信仰に配慮しつつ、日本の文化や生活習慣を理解してもらわなければなりません。そうしたことを含めて、日本の宗教がどのように対応するのかが課題になっているというわけです。

また、在留外国人の増加に伴って、外国人の児童生徒も年々増加しています。
文部科学省のまとめによると、2023年5月の時点で就学年齢に当たる外国人の子供の数は15万695人で、前回(2年前)の調査より約1割(1万3772人)増えています。
もちろん、こうした子供たちは、来日の理由、将来設計など置かれている状況はさまざまです。文部科学省は対応のため、『外国人児童生徒の受入れの手引き』を作成しています。
その中で、言語や文化の多様性について、「特に近年、学校生活で配慮すべき事項として宗教的な背景の違いがあります」として、一例としてイスラム教圏の子供たちの給食(豚肉を食べない)や体育の授業への参加、ラマダン(断食月)への対応などで保護者と事前に話し合い、基本的には保護者の宗教的判断を尊重すべきだと述べています。
それと共に、学校では日本人の児童生徒が各宗教や異文化への理解を深めることも大切でしょう。
各宗教の基本的な教えや儀式、宗教の違いについて、少なくとも知識としての教育が必要になります。私たちの日常生活の根底にある宗教や文化を知ることなしに多文化共生を唱えても、実際は難しいのではないでしょうか。
ただ、宗教や文化を学んでも、それが過去のもの、あるいは自分とは関係ないものになってはあまり意味がありません。
以前も紹介しましたが、日本の教科書では、宗教は“今も生きている”ものではなく “歴史・伝統を作ったもの”として扱われる傾向があります。
例えばドイツの教育は、宗教に正面から向き合うことで、同じ街、同じ学校の中の異教徒の存在を可視化していますが、日本の教育は逆に目立たせない傾向があるということです(『世界の教科書で読む〈宗教〉』)。
身近に信仰を持つ人がいると自覚することで、外国人児童生徒の学校への適応や居場所の確保につながり、多文化共生にもつながる可能性があるのではないでしょうか。