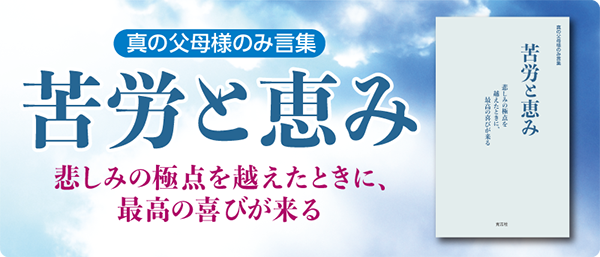ダーウィニズムを超えて 119
無神論を超えて⑤ 心の起源について
2025.07.13 22:00
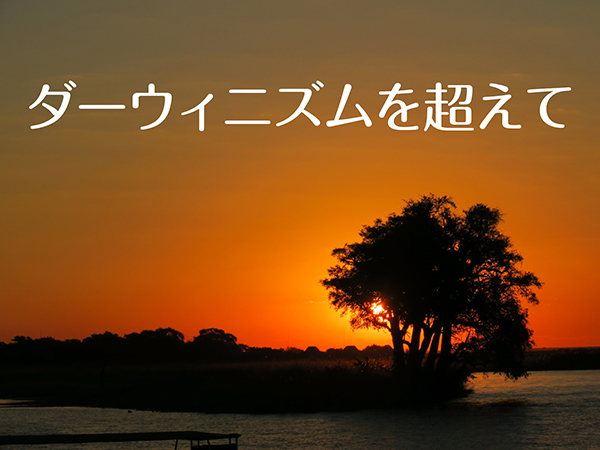
ダーウィニズムを超えて 119
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「ダーウィニズムを超えて」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。
生物学にとどまらず、社会問題、政治問題などさまざまな分野に大きな影響を与えてきた進化論。現代の自然科学も、神の創造や目的論を排除することによって混迷を深めています。
そんな科学時代に新しい神観を提示し、科学の統一を目指します。
統一思想研究院 小山田秀生・監修/大谷明史・著
第九章 科学時代の新しい神観
(一)科学時代における神の再発見
(3)無神論を超えて
5. 心の起源について
ギリシャ時代以来、中世時代を通じて、心と体は別のものであるという心身二元論的な考え方が支配的であった。そして心は神に通じる神秘的な領域とされていた。ところがルネサンス以後、自然科学の発展に支えられて、人体解剖が行われ、脳の構造が調べられるようになり、今日、神経生理学は脳の仕組みを細胞レベルで解明するに至ったのである。そして神経生理学者たちの多くは、心は脳の機能そのもの、または脳の生み出した産物であると主張しているのである。ここにおいても精神と神の存在が排除されたかのように見える。
しかしながら、脳の機能を物理的に解明する研究を積み重ねた結果、人間の心の動きは脳の機能または産物としては説明できないという主張もある。ここで二人のノーベル賞を受賞した大脳生理学者の見解を紹介しよう。
ロジャー・スペリー(Roger Sperry)によれば、心は脳の物理的現象を超える何かであり、心は物質の上位にあるという。しかしスペリーの場合、脳から分離した心というものは認めていない。一方、ジョン・エックルス(John C. Eccles)は、ワイルダー・ペンフィールド(Wilder Penfield)と同様に、脳をコンピューターにたとえれば、それを操るプログラマーに相当する心または魂が存在しなくてはならないと言う。
私たちひとりひとりの人格に独自性を与えるのは、自我の唯一性にほかならない。そして、自我とはすなわち魂のことであり、それは、自然神学的な意味での神の摂理によって、胎生期のいつかに私たちの肉体に宿るのだと著者は信じる。自身の心の奥底に、自分を真に自分たらしめている何かの存在を確信するとき、神の手になる魂の存在を、人はもはや疑いえなくなるのである。私たちの脳は、驚くべき生物進化のプロセスが創り出した、素晴らしいコンピューターであり、私たちの心はそれを操るプログラマーである。私たちはこのコンピューターを生涯の道連れとして、この世を生きていく。それは私たちの自我が、あるいは魂が、共にこの物質世界に身を置いて交わり合い、成長していく道程である。そしてその道程に、私たちは限りない神秘を見いだすのである(*12)。(太字は引用者)
このように、最先端の大脳生理学においても、神は片隅に追いやられているかのようであるが、決して排除されたわけではない。むしろ神の復権の時が近づいているのである。
*12 ジョン・エックルス、ダニエル・ロビンソン、大村裕他訳『心は脳を超える』紀伊国屋書店、1989年、80~81頁。
---
次回は、「精神と物質の根源としての神」をお届けします。
◆『ダーウィニズムを超えて』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ