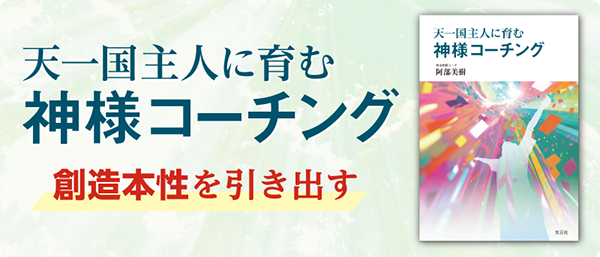ダーウィニズムを超えて 118
無神論を超えて④ 生命の起源について
2025.07.06 22:00
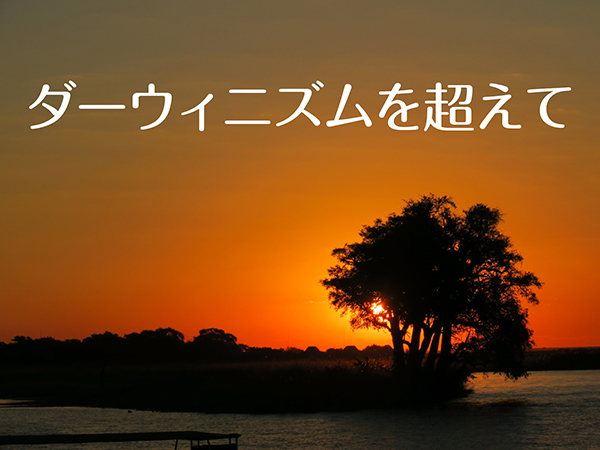
ダーウィニズムを超えて 118
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「ダーウィニズムを超えて」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。
生物学にとどまらず、社会問題、政治問題などさまざまな分野に大きな影響を与えてきた進化論。現代の自然科学も、神の創造や目的論を排除することによって混迷を深めています。
そんな科学時代に新しい神観を提示し、科学の統一を目指します。
統一思想研究院 小山田秀生・監修/大谷明史・著
第九章 科学時代の新しい神観
(一)科学時代における神の再発見
(3)無神論を超えて
4. 生命の起源について
進化論者は、生命の発生のプロセスを次のように説明している。今から約46億年前、原始の地球をおおっていた原始の大気は、メタン、アンモニア、水蒸気、水素、窒素などから成っていた。原始の大気に紫外線、宇宙線、自然放電(雷)などが作用することによって、アミノ酸、糖、核酸塩基、有機酸などが生じた。これらが雨に溶けていき、蓄積されて「有機物のスープ」をつくった。スープの中でアミノ酸はつながってタンパク質となり、核酸塩基は糖、リン酸と結合してヌクレオチドとなり、さらにヌクレオチドはつながって核酸(RNAとDNA)となった。やがて原始細胞膜が出現し、核酸、タンパク質、膜から成る原始細胞ができた。そして核のない原核細胞から、核のある真核細胞へと進化し、ついには細胞分裂を行うことによって多細胞生物へと進化したというのである。
水蒸気、水素、アンモニア、メタンなどの混合気体に、放電、熱、紫外線、宇宙線などのエネルギーを与えると、生体を構成するアミノ酸や核酸塩基ができることはすでに実験的に確かめられている。しかし、ここまでは単純なプロセスであり、生命体の材料となる有機物質ができるだけである。これらが生命の発生とかかわってくるためには、核酸とタンパク質(酵素)ができなければならず、それは非常に困難なプロセスである。
アミノ酸やヌクレオチドがつながっていくプロセスは、水溶液の中で水を除きながら行うものであって、それは実験的にはとても困難であり、そういうプロセスの最初の段階がどのようにして始まったのか、謎に包まれている。
ところで最近になって、原始地球の大気は水蒸気、水素、メタン、アンモニアのような水素化合物が主ではなく、主成分は二酸化炭素だったという可能性が高まってきた。それにより生命は、「空中放電」と浅海の「有機物のスープ」からできたのではなくて、遠洋の深い海底で生まれたという説が注目を浴びている。実際、深海の熱水鉱床では、酸素ではなく硫化水素を使ってエネルギーを得るバクテリアが生息しているのである。しかしそうであっても、核酸とタンパク質がいかにしてできたのか、依然として謎のままである。
核酸には遺伝暗号が含まれているが、4種類の核酸塩基の配列の仕方が遺伝暗号になっている。その遺伝暗号の情報によって、カエルの卵はカエルに、ニワトリの卵はニワトリに成長する。しかしこのような驚くべき内容をもった遺伝暗号が、何によって生じたのかということも、大きな謎である。
フランスの生化学者ジャック・モノー(Jacques L. Monod)は「遺伝子暗号および翻訳機構の起源は全くの謎である(*8)」と言い、イギリスの科学評論家のフランシス・ヒッチング(Francis Hitching)も「遺伝暗号の起源については生物学者は明らかに何も知らない(*9)」と言っている。
さらにまた、生命の起源において避けて通れない難問がある。生命の発生には核酸とタンパク質が必要であるが、核酸はタンパク質(酵素)の働きによってつくられ、タンパク質は核酸のもつ情報によってつくられる。したがって「核酸が先にできたのか、タンパク質が先にできたのか」という問題は「卵が先か、ニワトリが先か」という問題と同じであって、堂々めぐりになってしまう。この問題についても、明確な解答はなされないままである。
細胞の核の中ではDNA情報がRNAに転写され、それが読み取られることでタンパク質がつくられている。そしてタンパク質から成る酵素の働きによって細胞の代謝などさまざまな機能が営まれているのである。そのように細胞の中ではDNA→RNA→タンパク質という順序で移行しているが、最近では最初の生命は自己複製(遺伝情報の役割)と代謝(酵素の役割)をもつRNAから始まったという「RNAワールド」説が有力視されている。さらにはタンパク質そのものが遺伝情報を伝達していた「タンパク質ワールド」から始まったという説まであるが、混迷を深めるばかりである。
リボザイム研究の国際的な第一人者である、アメリカ、スクリプス研究所のジェラド・ジョイス(Gerald Joyce)も、科学雑誌『ニュートン』(2007年3月号)のインタビューのなかで、「生命の起源について、博士のシナリオを聞かせてください」という質問に対して、「読者のみなさんをがっかりさせるかもしれませんが、私には分かりません。科学界のだれにも分からないのです」と率直に答えているのである(*10)。
このように、生命の発生の問題も、偶然的な自然発生と見る限り、謎のままである。しかし、神の設計図(ロゴス)が遺伝暗号としてDNAの中に組み込まれていると考えれば、その謎はきれいに解ける。そして核酸とタンパク質も、どちらが先かというのでなくて、同時的に、生命をつくるために準備されたものと見ればよいのである。
生命の発生におけるもう一つの謎に左右の非対称の問題がある。化学反応機構の研究者であるイギリスのチャールズ・スターリング(Charles Stirling)は次のように語っている。
そもそも人間は左右対称ではない。顔も右半分と左半分では微妙に違うし、心臓は左。脳は左半球が右半球よりも大きく、左右の機能も異なる。なぜ、こうなったか誰も知らない。……地球上の生き物の身体をつくっている20種類のアミノ酸は、なぜかすべて左型である。生命の起源をめぐる最大の謎だ(*11)。
この問題もやはり、パストゥール(Louis Pasteur, 1822~1895)が「宇宙は非対称である」と述べたように、創造主の特性に起因するものと見ればよい。すなわち、主体と対象の二性をもつ神によって造られた世界であるから、主体と対称の関係が右と左の非対称として現れるということである。
*8 ジャック・モノー、渡辺格・村上光彦訳『偶然と必然』みすず書房、1972年、166頁。
*9 フランシス・ヒッチング、樋口広芳・渡辺政隆訳『キリンの首』平凡社、1983年、87頁。
*10「ニュートン」2007年3月号、55頁。
*11「読売新聞」1993年7月4日。
---
次回は、「無神論を超えて⑤ 心の起源について」をお届けします。
◆『ダーウィニズムを超えて』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ