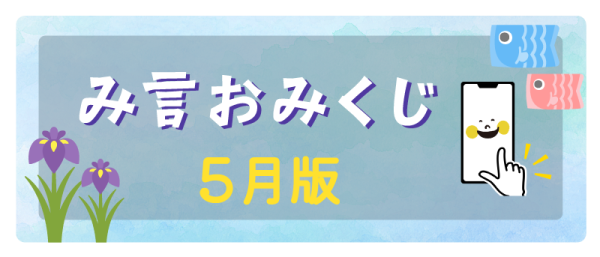心霊を育てる生活原則 206
真を求めよ
2025.05.02 17:00
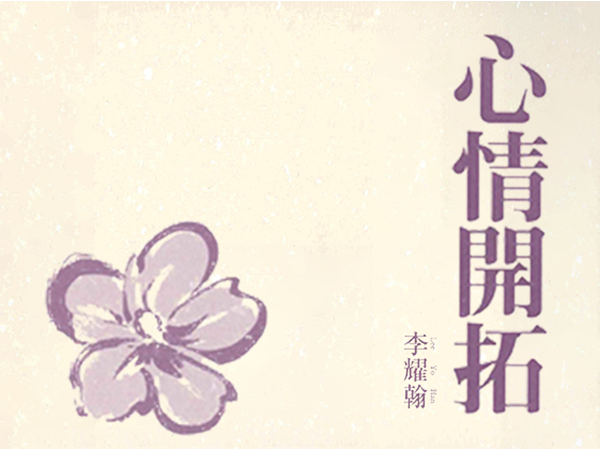
心情開拓
心霊を育てる生活原則(206)
原理を生活化するために、李耀翰(イ・ヨハン)先生(1916~2019)が信仰のイロハを日本人の心情を分析しながら説かれた講話集、「心情開拓~心霊を育てる生活原則」を毎週金曜日配信(予定)でお届けします。
家庭連合の教会員の皆さまはもちろん、世代を超えて多くのかたに読んでいただきたい書籍です。
李耀翰・著
24 真を求めよ
(1994年10月23日 札幌教会)

真のお父様の祈祷文を拝読します。
「お父様! 行き、また行く道が険しいと言えましょうか? 私たちの心は、お父様のその心情の切なさと比べることができませんし、私たちの悔しさは、幾重にも横たわったサタン圏を歩まれたお父様のその足跡と比べられないことが分かるように許諾してください。
険しい道を行きながらも、天のみ旨に責任をもつための使命感が私たちの心にわき上がるように許諾してくださり、悲しみながらもお父様の悲しい歴史の友となって、あなたの路程に同伴することのできる息子、娘となるように許諾してくださり、悔しい心情に同伴して友となることができ、お父様の内的悲しみの友となると同時に、外的悲しみの友となって、永遠なるお父様の喜びの対象となることができるように許諾してください」(文鮮明先生古稀紀念文集3『文鮮明先生の祈祷』祈祷240より)。
この祈祷文をけさの説教の本文として、そこから恨みの歴史の同伴者としての勝利というポイントを取って、「真を求めよ」という題目にしました。
神様の悲しい心情
お父様は最近、「真を求めよ」というみ言(ことば)をよく語られますが、私たちが真を求めにくい理由は、私たちに堕落性がにじんでいるからです。真という考え、願いは簡単にもつことができますが、自分の堕落性を清算しながら、どういうふうに真の心情を自分の本性に芽生えさせるかということが、私たちが生活の中で取り組んでいくべき問題です。
まず、私たちは創造主を知らずにいました。堕落という出来事を通じて、その時、創造主の心情がどうであったかを考えてみます。その時の神様の心情は、家庭の中で悲しいことがあった場合に例えることができます。家庭関係、夫婦関係、親子関係で悲しむ時とはどういう時かというと、激しくお互いに逆らった時、葛藤(かっとう)した時、あるいは自分勝手なことをした時です。関係をもっているということは、自分を肯定することができない立場であるということです。それなのに、自分勝手に振る舞った場合には、悲しみを感じるのです。
創世記の第3章9節に、神様がアダムを訪ね回った話があります。神様は、「アダムよ、どこにいるのか」と、アダムを捜されたのです。しかし、どこにいるか分からないから捜したのではなく、勝手なことをして隠れているアダムに向かって、「どこにいるのか」と捜されたのです。その言葉の背後には、神様の説明できない悲しみがあります。
私たちの家庭の中で勝手なことをした人に対して話す時も、この悲しみと同じなのです。だれがだれに許諾を受けた生活なのかというのが問題なのです。「どこにいるのか」、「だれがお前にそんなことをさせたのか」。神様からこういうふうに聞かれた時に、アダムは何とも答えられない恥ずかしい、弁解することができない立場に立っていました。アダムは、「自分がした」とは言わないで、「エバがしたのだ」と言い、エバは「天使長がした」と、このように転嫁していったのです。
私たちは、そういう時にはよく、アダムが神様の悲しみや悔しい心情を知らなかったからだと言います。「あなたはどこにいるのか」という神様の言葉の背後に、聖書には表れていませんが、神様の悔しい心情があるのです。お父様が神様の立場、心情を話されるまでは、私たちもそのような神様の心情を知っているようで、実は知らずにいました。
それから伝道の書第7章28節には、「わたしはなおこれを求めたけれども、得なかった。わたしは千人のうちにひとりの男子を得たけれども、そのすべてのうちに、ひとりの女子をも得なかった。見よ、わたしが得た事は、ただこれだけである」とあります。
聖書の聖句を一つ一つ、このような神様の心情を分かって読んでいくと、「わたしは千人のうちにひとりの男子を得たけれども、そのすべてのうちに、ひとりの女子をも得なかった。見よ、わたしが得た事は、ただこれだけである」という言葉の背後にも、とても悔しい神様の心情が含まれているということが分かります。聖書を再び読んでみると、神様が人間に対して話される言葉はみな、恨(ハン)をもった心情で話されていることが分かります。
ノアに向かって話す時も、アブラハムに向かって話す時も、みな悲しみに包まれて話されたのです。アブラハムも、その言葉の背後に神様の悔しい心情があるから、何とも答えられなかったのです。アブラハムが、神様の命令にあれほど絶対服従したのは、自分の信仰からという面もありましたが、神様の言葉の背後に悔しい内容があることを感じ取ったからではないでしょうか。ですから、「アブラハムよ、そのカルデヤのウルから出てきなさい。出発しなさい」という一言で、びっくりして目的も知らずに出発したのです。
お父さんがあまりにも悔しくて子供を呼んだ場合、子供は勝手なことをして良心の呵責(かしゃく)があって恥ずかしくて隠れていたとはいっても、「お前、出てきなさい」と言われた時には、「なぜ出てこいと言うのですか」とは言えません。「なぜ強制的に呼び出すのですか」とは言えません。それは、自分がお父さんを悲しませた理由を知っているからです。
それと同じく、アブラハムも神様に召命された時に絶対服従したというのは、神様の悲しみに圧倒されたからです。神様の心情を知らなければ、それは強制的な言葉に聞こえますが、神様はアブラハムを呼び出した時、本当に悲しい心情に包まれて、命令せざるを得なかったのです。
---
次回は、「イエス様の悲しみ」をお届けします。
◆『心情開拓』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ