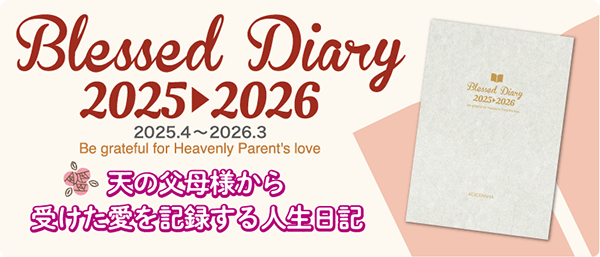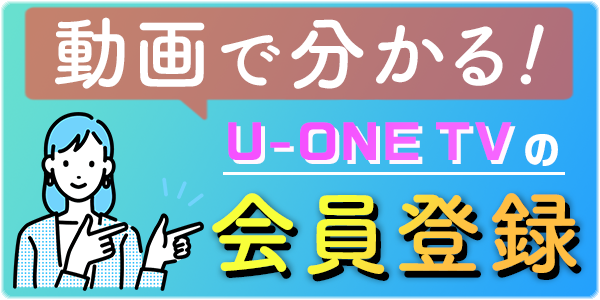「宗教」を読み解く 361
母なるもののとりなし
2025.04.08 17:00

シリーズ・「宗教」を読み解く 361
母なるものを慕い求めて⑤
母なるもののとりなし
ナビゲーター:石丸 志信
「聖母マリア」という呼称は、キリスト教徒たちが体験してきた創造主なる神の母性的な愛を表現しようとしてきたものではないかと思える。
カトリック教会の教えでは、神の独り子、イエス・キリストの誕生に関わる重要な役割を果たした女性として「恵みに満ちたかた」「神の母」と称えている。
また、従順、謙遜の徳をもって、人類の救いに協力したかたとして「新しいエバ」という表現も用いられている。
「教会論」の文脈では、「教会の母」として弁護者、扶助者(ふじょしゃ)、仲介者の役割を果たしていると教えている。
一般信徒の信仰生活においては、聖母マリアのとりなしを願う祈りである「アヴェ・マリアの祈り(天使祝詞)」を覚え、折に触れて唱えてきた。
以前は、文語調の訳語があてられ、このように祈った。
めでたし、聖寵(せいちょう)充満(みちみ)てるマリア、
主 御身(おんみ)と共にまします。
御身は女のうちにて祝せられ、
御胎内の御子(おんこ)イエズスも祝(しゅく)せられ給(たも)う。
天主の御母(おんはは)聖マリア、
罪人なるわれらのために、
今も臨終の時も祈り給え。
アーメン
(『公教会祈祷文』カトリック中央協議会編 中央出版社 昭和23年)
現在はより平易な口語訳が用いられているが、それは次のようになる。
アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、
主はあなたとともにおられます。
あなたは女のうちで祝福され、
ご胎内の御子イエスも祝福されています。
神の母聖マリア、
わたしたち罪びとのために、
今も、死を迎える時も、お祈りください。
アーメン。
(2011年 6月14日 定例司教総会にて承認/©日本カトリック司教協議会)
ルカによる福音書の第1章に記された、マリアが洗礼ヨハネを宿したエリザベツを訪問した時、聖霊に満たされたエリザベツの叫んだ賛美の言葉が基になっている。
ラテン語の「Ave Maria」の歌詞には、バッハ、グノー、モーツァルト、シューベルトなど多くの作曲家が美しいメロディーを付け、声楽家は好んで歌ってきた。
50粒の数珠を繰りながら祈る「ロザリオの祈り」は、「アヴェ・マリアの祈り」を1環50回、続けて3回繰り返す中で、2000年前に成された神の御業(みわざ)を思い起こしていく。この祈りの形式も、修道院から生まれ、一般信徒に普及した。
修道者も信徒らも、母なるものに向かって心を開き、自らの足りなさを悔い、罪人である己(おのれ)の人生を、主イエス・キリストに全面的に委ねていこうとした。
時にロザリオを繰りながら祈り続ける中で、そこはかとない希望や喜びを感じ、慰めや励ましを感じて生きてきた人は多い。
人々はそれを、聖母のとりなしとして受け止め感謝する。その内的体験はまさに聖霊によって愛と慰めを受け、活力を回復し、生命の復活を体験していることにほかならない。
★おすすめ関連動画★
ザ・インタビュー 第22回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その1)「超宗教運動の30年を振り返って」】
ザ・インタビュー 第23回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その2)「宗教者の対話を促進する『超宗教フォーラム』」】
ザ・インタビュー 第24回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その3)「宗教者の役割と祈りの重要性」】
ザ・インタビュー 第25回
【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その4)「超宗教平和運動への召命」】
---
U-ONE TVの動画を見るにはU-ONE TVアプリが必要です!
無料ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ダウンロードはコチラから