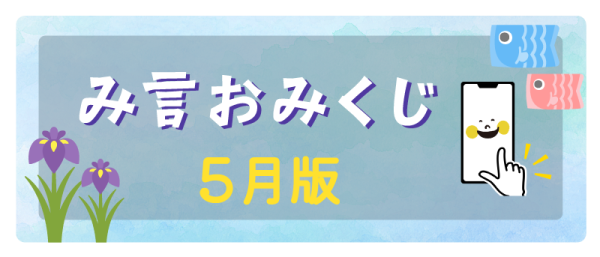青少年事情と教育を考える 289
子育て支援が4月から充実?
2025.04.18 17:00

青少年事情と教育を考える 289
子育て支援が4月から充実?
ナビゲーター:中田 孝誠
「こども・子育て支援 2025年4月から さらに充実します」——。
こども家庭庁が、ウェブサイトでこのようにうたっています。
何が充実するのか? 具体的には次のような支援策が挙げられています。
一つの柱になるのは「伴走型相談支援」です。妊娠期から寄り添い、出産・育児の相談に応じて支援を充実させるというものです。
次に「妊婦のための支援給付」です。妊娠届出時に5万円を給付するなど経済的な支援です。
また、両親が共に育休を取った場合は手取り10割相当が支給されます。
親の体調面や育児の悩みなどを相談できる「産後ケア事業」の環境整備もあります。

保育園の関係では、「こども誰でも通園制度」の制度化です。生後6カ月から満3歳未満の子供が時間単位(子供1人あたり月10時間)で保育所を利用できるというものです。
また、児童数に対する保育士の配置が厚くなります。1歳児5人に保育士1人(現在は6人に1人)、4、5歳児は25人に保育士1人(現在は30人に1人)の体制になります。「安心してこどもを預けられる保育環境」を整備するというものです。
この他、子供の生活支援や学習支援のさらなる充実、障害の有無にかかわらず全ての子供が安心して共に育ち暮らすことができる地域社会づくり、子育て世帯への訪問支援や食事提供など多様なアウトリーチ支援があります。
さらに、子供3人以上の世帯の大学等にかかる教育の支援拡充などもあります。
これらの施策は、親子への切れ目のない支援となれば効果的だと思われます。
ただし、課題もあります。例えば「こども誰でも通園制度」は、親の気分転換などにはいいのですが、受け入れる保育士の負担、人材不足が懸念されてきました。
大学教育の支援も、子供が3人いても1人が扶養から外れたら対象外になるなど、支援は限定的です。高校の無償化もそうですが、教育無償化には批判的な意見が少なくありません。
出生数は昨年、初めて80万人を下回り、過去最低の72万人となりました。生まれてきた子供たちを大切に育てるために、子育て支援策の効果を確認していく必要があります。