日本人のこころ 31
東京・福島─高村光太郎『智恵子抄』
2020.12.27 17:00
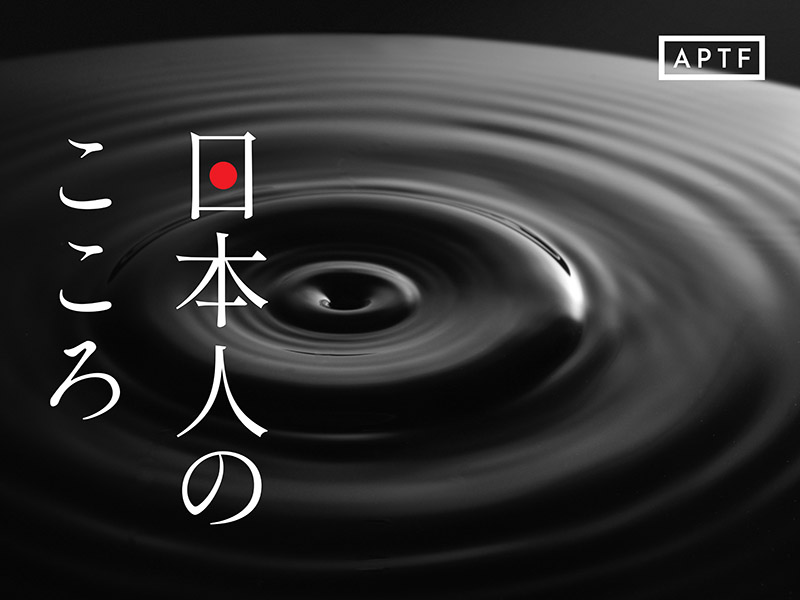
日本人のこころ 31
東京・福島─高村光太郎『智恵子抄』
ジャーナリスト 高嶋 久
一ばんぢかに永遠を感じる
憧れの純愛と現実の性愛との間で揺れ動く高校時代、私が愛読していたのが朱色の表紙も鮮やかな『智恵子抄』です。中でも「僕等」の「僕はあなたをおもふたびに/一ばんぢかに永遠を感じる/僕があり あなたがある/自分はこれに尽きてゐる/…」というフレーズに強く引かれました。
有限で相対的な存在の人間が、なぜ永遠性や絶対性を求めるのかが大きな疑問でした。工学系の技術者にでもなろうかと受験勉強をしながら、それに飽き足らない自分を感じていたのです。清楚な同級生の女性を憧憬しながら、官能的な女子高生に心を奪われたり、それなりの青春でした。振り返ってみると、自分の中にある女性像の揺れがそのまま反映されていたにすぎないことに気づきます。母親との間で形成され始めた男子の女性像は、年齢を重ね、いろいろな女性とふれあうことで成長していくのです。
50代になって訪れた福島県二本松市の二本松城址に高村光太郎の詩碑があり、ここが智恵子の生まれ故郷だったのに気づきました。詩碑の向こうには、智恵子が愛した阿多多羅山が見えていました。
高村光太郎は明治16年、東京で、上野公園の「西郷隆盛像」などで知られる近代彫刻家・光雲の長男として生まれます。父の背中を追って彫刻家を志望し、東京美術学校彫刻科に入学、さらに西洋画科に再入学して油絵も学びました。その後、ロダンの「考える人」に衝撃を受け、西洋の彫刻技術を学ぶためニューヨークやパリなどに留学します。
光太郎が芸術と同じくらい打ち込んだのが文学で、与謝野鉄幹が主宰する『明星』にたびたび寄稿し、「僕の前に道はない/僕の後ろに道は出来る/ああ、自然よ/父よ/僕を一人立ちにさせた広大な父よ」(「道程」)で知られる詩集『道程』を出版し、作家としても世に知られるようになります。
もっとも、光太郎にとって本来の仕事は彫刻で、詩については、彫刻の純粋さを守り、彫刻に文学など他の要素が入らないようにするための「安全弁」と考えていたようです。父のような仏師上がりの職人的彫刻家にはなれず、気に入った仕事がないと、翻訳で暮らしをしのいでいました。
「道程」で気になるのは、自然に対して日本的な「母よ」ではなく「父よ」と呼びかけていることです。これには、「僕の青春らしい青春は、パリから始まったような気がする」と述懐しているように、強烈なフランス、西洋体験があります。当時のフランスは、19世紀後半からの芸術運動のメッカで、とりわけロダンは近代彫刻の改革者でした。ミケランジェロの理想の肉体美を復活させ、自然主義的方法とロマン主義的感性により、人間の生命と情熱を普遍的な彫刻に表現したのです。ロダンを通して父性的な西洋文化の真髄に触れた光太郎は、父親に代表される東洋文化との違いに愕然とさせられます。

いつも智恵子と一緒
智恵子は明治19年、福島県安達郡の富裕な造り酒屋・長沼家の長女として生まれます。上京して日本女子大学家政学科に入ると、洋画家を志望するようになり、一級先輩のテニス仲間だった平塚らいてうが明治44年に創刊した『青鞜』の表紙を描いています。同年末、智恵子が光太郎のアトリエを訪ねたのが初めての出会いで、やがて引かれ合うようになります。
洋画家としての自立がおぼつかなく、父の勧める結婚のため福島に帰ろうとする智恵子に投げ掛けた光太郎の詩が『智恵子抄』冒頭の「人に」です。「いやなんです/あなたのいってしまふのが──/……おまけにお嫁にゆくなんて/よその男のこころのままになるなんて」。この詩を読み、智恵子は光太郎と生きることに決めます。
2人の間には『智恵子抄』に見られるような純愛もありましたが、光太郎には一方的に理想の女性像を智恵子に求める面がありました。病弱だった智恵子は光太郎と暮らしながら、1年のほぼ半分は実家で過ごし、やがて精神を病むようになります。「智恵子は東京に空が無いといふ、/ほんとの空が見たいといふ。……」の詩を光太郎は「あどけない話」と題していますが、実は統合失調症の兆候でした。
さらに智恵子の実家が破産したことで、智恵子の精神はますます病み、薬物自殺を図るまでになってしまうのです。そして昭和13年、肺結核によって52歳で亡くなり、『智恵子抄』が出版されたのはその2年後でした。
戦時色が強まり、太平洋戦争が始まると、光太郎は智恵子のことを忘れるかのように戦争賛美の詩を発表するようになります。思想的には西洋礼賛から日本回帰で、仏像彫刻も再評価し、名実ともに父の後継者となります。
空襲で家とアトリエが焼けてしまった光太郎は、宮沢賢治の縁故で岩手県花巻の郊外に疎開し、戦後もさらに山奥の小屋に移り、農民に教えを乞いながら自給自足の暮らしを始めます。自然に即した暮らしが、禅も学んだ光太郎の最後の願いだったのです。訪ねてきた知人に、寂しくはないかと聞かれ、「いつも智恵子と一緒にいるから少しも寂しくない」と答えています。
70歳になった光太郎は、青森県十和田町の町長から十和田湖のほとりに銅像を建てるよう依頼されました。光太郎がそれを承諾したのは、智恵子の姿を後世に残したいと思っていたからです。こうして昭和28年、光太郎が智恵子観音像と呼ぶ「乙女の像」が十和田湖畔にたたずむようになったのです。



