スマホで立ち読み 第38弾!
“人さらい”からの脱出 20
逃げ回る生活の始まり⑤
2025.08.27 22:00
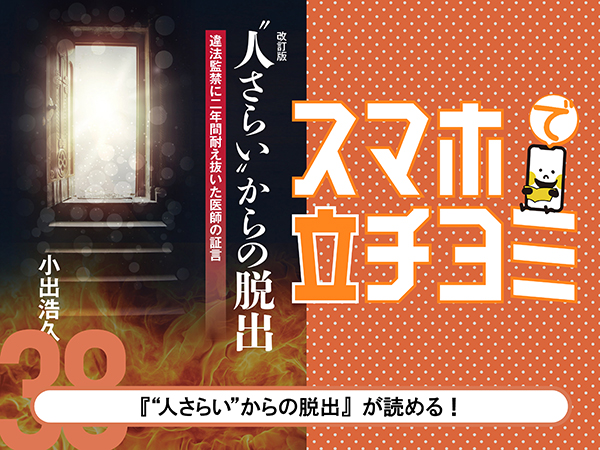
スマホで立ち読み Vol.38
『“人さらい”からの脱出』20
小出浩久・著
スマホで立ち読み第38弾、『“人さらい”からの脱出』を毎週水曜日(予定)にお届けします。
2年間にわたる拉致監禁後、「反統一教会グループ」の一員として活動した経験のある筆者。そんな筆者が明らかにする、「脱会説得」の恐ろしい真実とは。
---
第1章 15カ月間の監禁生活
四、新潟での説得、逃げ回る生活の始まり⑤
ここで、少し長くなるが、これらの書物を通じて私の感じたことを、まとめておきたいと思う。
私は、『原理講論』や文(ムン)先生のみ言(ことば)を学び、実践してきたのであるが、実はある限界にぶち当たっていた。
『原理講論』には、人間と宇宙は神様が喜ぶために創られたとある。それならば私たちの目指す理想世界は、究極的には、喜びの満ちあふれる世界にならなければならないのに、私の中にその青写真がはっきりとしていなかった。『原理講論』だけを幾度繰り返して読んでも青写真はある程度にしかならなかった。
理想世界では、働くことはもちろんのこと、科学を研究すること、芸術を楽しむこと、思索に耽(ふけ)ること、旅すること、すべてが神と人との喜びとなるはずであった。
しかし、現実の世の中を、そして、いま理想世界を目指しているはずの自分自身を、見つめてみると、余りにも喜びということから離れていた。
たとえ現実がそうなっていなかったとしても、(神様の)創造理想さえ、はっきりつかめていたなら問題なかった。しかし、『原理講論』の中に示されているものだけでは満足できない状態であった。
私は統一思想を読み、その明快さに驚いた。(宮村氏から最初に内容を問いつめられた)原相論というところには、神様の創造のプロセスがより詳しく、理性的に納得できるように書かれていた。そこでは創造のプロセスを、ロゴスの形成と新生体の形成という二段階に分けていた。ロゴスの形成とは、人間でいうならば、構想、設計図を考える段階に当たる。
被造世界の構想はただ一回で決定してしまったのではなく、構想を「練り直すこと」もあったというのである。
さらに、原相論には、神の創造の理由が以下のようにはっきりと表現されていた。
「愛を通じて喜びたい」という、何ものによっても抑えがたい衝動、それが神の創造の理由である。特に、我が子として人間を創造され、その子を愛したいという抑えがたい衝動をもっておられた。
そして、被造世界の構想を考えるときも、実際に生み出すときも、片時も、この喜びへの衝動という出発点から外れることはない。これらのことは具体的に表現すると、我が子、アダムとエバを心に描きながら、宇宙そして地球のすべてを、アダムとエバの喜びのために、「あれがいいか」「これがいいか」と構想を練り直しながら、能力のすべてを投入してつくられたということである。
本性論のところを学んだときは、神の似姿としてつくられた人間の本性も、原相論での神性と同じく、片時も愛と喜びから離れることはできないことが、頭の中できちんと整理された。そして、学ぶこと、考えること、仕事をすること、スポーツすることetc、すべてが愛と喜びのうちになされうることがようやく分かった。
喜びのために「愛し、愛されたい」という想いが、誰のうちにも与えられているので、「愛し、愛される」中に最高の喜びが湧いてくることも納得がいった。子供は親に愛されたいという抑えがたい衝動をもち、愛し合うことを願い、親になれば、子供の喜びのためにすべてを投入したいと願うようになる。そのように創造されたと書かれていた。
監禁されているという追い詰められた環境で、統一思想を学び、理解することができたことに、神様の大きな愛を感ぜずにはいられなかった。
さらにこのとき、『共産主義の終焉(しゅうえん)』で勝共理論を深く学んだ。
共産主義理論は、若者の心、特に、人生の矛盾および社会の矛盾に悩んでいる若者の心をとらえる力があった。
私自身も共産主義に魅力を感じたことがあった。
高校時代、倫理社会の教師は、半年間、狭山事件を考えさせたのち、残りの半年間、人間疎外論から始まって、唯物弁証法、唯物史観、労働価値説など、マルクスの共産主義理論のあらましを講義した。また、世界史では、ロシア革命についてかなり詳しく講義があった。世界史の先生から、「全世界のプロレタリアートよ! 団結せよ!」と語られたときは、大学に入ったなら、共産主義をかかげる団体に一度は触れてみたいと考えた。しかし、私の入った大学は地方の医科の単科大学であったので、そういう団体が一つもなく、その考えは実行されなかった。
一つのユートピアを目指した思想によってソビエト連邦、東欧、中華人民共和国などの国家が変革されたというのは歴史的事実である。しかしながら、それらの国家の侵略的性格、指導者の独裁、経済的困窮なども明らかだった。一体どういうことなのだろうか?
その疑問に人間の心理をも考察して理論的に答えてくれるのが、この『共産主義の終焉』という書物であった。まず、マルクスがどのようにその思想を形成していったのかを分析し、理論の一つ一つの誤謬(ごびゅう)も明らかにし、なぜ、その理論による国家が悲惨な状況になってしまったかを論理的に説明してくれている。この勝共理論を学ぶことにより、統一思想が今までのどんな哲学よりも共産主義理論を説明する力において優れていることがはっきりと分かった。
マルクスはどうして共産主義理論をつくりあげたのか?
彼を執拗(しつよう)に追い詰めるプロシア(ドイツ)に対する“憤激の情念”が彼をして革命論へと駆り立てていったのであった。
さらにもとを正せば、幼少期からの宗教への憎悪と反抗心、神の否定、神への復讐、そういう思いがマルクスの思想形成の根本的動機となっていた、との説明はよく納得できた。
その理論に従った共産主義者たちが、怨念と復讐心理を原動力としながら、はじめはプロレタリア階級の代表、人民の代表を自称しながら、結局は自己中心的な愛と欲望に支配されて、人民の抑圧者に変わっていったのは、しごく当然だった。
勝共理論を学ぶこと、そして、共産主義国家の現実を見つめることを通して(折しも、金賢姫〈キム・ヒョニ〉の北朝鮮の実態を示す告白書、東欧諸国が監視国家であった実態をあかすテレビ番組、書籍などが多数あった)人間の生活、人間社会にとって、宗教、無形なるものへの畏敬の念、そしてさらには、神の愛が絶対的に必要であることがはっきりと分かった。(神の愛は現実生活の中では、親の愛、父母の愛としてあらわれてくるもので、宗教というものに限定されるものではないと思う)。
共産主義という徹底した無神論による歴史的大失敗によって、それは私ばかりでなく多くの人の目に明らかとなったはずである。
この勝共理論を学ぶことで、統一原理が宗教哲学を志す人たちだけでなく、政治的な指導者にとってもぜひとも必要であることが良く分かった。2021年1月のNHKの番組「100分de名著」に、『資本論』(カール・マルクス著)がとりあげられていて、今の現実社会の問題解決に彼の思想が有用だという考え方が紹介されている。日本の多くの人々は、ロシア、中国、北朝鮮の脅威を感じている。共産主義理論の悪なる本質をはっきり知らずして、希望は見えて来ないのが現代であると思う。この神なき宗教である共産主義に対して神の愛と真理をもって、徹底的に戦い続け、世界中(特にアメリカ)で活動してこられた文鮮明(ムン・ソンミョン)先生が世界人類の救世主であるという確信は確固としたものとなった。〈文先生がいかに共産主義と戦われたかについては、私が監禁から解放された後、出版された『神の代辯(だいべん)者』(田井友季子著 世界日報社刊)および『世界最強の新聞』(戸丸廣安著 光言社刊)に詳述されている。さらに詳しく知りたい方は、「主の路程」と『御旨と世界』について、学ばれれば良いと思う〉。
統一思想と勝共理論を学ぶことにより、統一原理そして文先生への確信は、自分個人に絶対必要という次元でなく、世界の指導者の方々にとって、歴史の先駆者の方々にとって絶対必要という次元にまで高まった。
(続く)
---
次回は、「逃げ回る生活の始まり⑥」をお届けします。
◆「一気に読んでしまいたい!」というあなたへ
『“人さらい”からの脱出』を書籍でご覧になりたいかたは、コチラから



