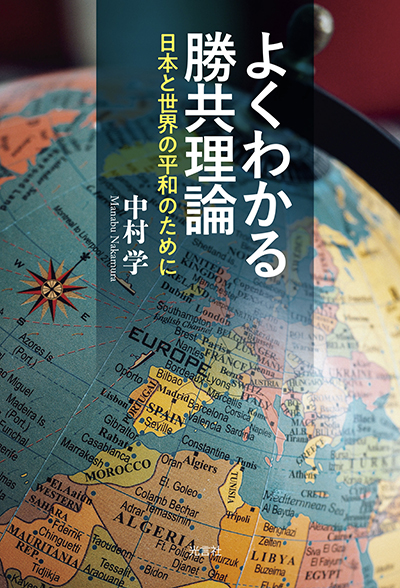ほぼ5分で読める勝共理論 91
政治家は国家観を持つべきである
2025.08.21 12:00

ほぼ5分で読める勝共理論 91
国家観②
政治家は国家観を持つべきである
編集部編
なぜ政治が必要なのか
政治家にとって一番大事なことは何か。それは、しっかりとした国家観を持っていることだと筆者は考えています。
今回はこの点について説明します。
民主主義国家では、政治家は国民の代表です。ですから政治家にとって大事なことは国民の思いや考えを知ることになるでしょう。
多くの人の話を聞いて共有し、それを政治の言葉で表現する。これは政治家にとって重要なことです。しかしそれだけでは、政治家は単なる利害の調整役にしかなりません。
例えば、Aさんが得をするとBさんが損をする。そういう場合にどうやって調整するか。
二人とも得をする方法はないのだろうか。そうやって落としどころを探すのは政治の重要な役割です。
しかし政治で扱うのはそういうことばかりではありません。むしろ少ないのです。
特に学生の皆さんの場合、「答えは一つしかないのが普通だ」と思う人も多いのではないでしょうか。
確かに学校のテストでは、答えは一つしかありません。
同様に、「社会で問題があってもみんなが協力して話し合えば話し合いは自然にまとまるのではないか」「一つの答えにたどり着くようになっているのではないか」、そんなふうに考えるかもしれません。
そしてその一つの答えを探し出すのが政治家の役割ではないかというわけです。
しかし政治の世界では、基本的に答えが一つということはありません。もし答えが一つならば、そこには争いがないので話し合う必要はなく、政治も必要ないということになります。
では、どういう場合に政治が必要かというと、一つの問題に対して答えがたくさんあり、しかもどれにもそれなりの根拠や理由があってどれが正しいと決められない場合です。
答えが出ないのは別に話が下手だからではありません。意地になって話し合いを拒んでいるからでもないのです。
そもそも、決められないようなものだからなのです。
国によって国家観は違う
例えば、米国と日本の国家観について考えてみましょう。
米国は、信仰の自由を求めて建国した国です。従って、自由をとても大事にします。大成功すると大金持ちになって、そうでない人は貧しいままです。それが自由の結果だと考えます。
福祉を充実させるよりは、ボランティアに任せます。自発的であってこそ、自由が尊重されていると考えるからです。
つまり、貧富の差や貧困があっても、国がなんとかしようというよりも、自由に解決させることが大事なのだと考えます。米国とはそういう国です。
日本ではそう思わない人が多いのではないでしょうか。
・貧富の差は良くない。
・国は福祉をもっと充実させるべきである。
・社長と労働者も家族のようなものである。みんなで富を分かち合うのが家族(共同体)である。
日本人は一般的にこのように考えるのです。
筆者はこういう日本の価値観は、縄文時代の頃からあったのではないか、そして聖徳太子の時代にすでに言葉としてまとめられていたと思っています。
このように、私たちが当たり前のように思っていることでも、国によって国家観は違うものなのです。そしてどちらが正しいという答えはありません。
これが国家観です。
日本では国家観について誰も教えてくれないので、なかなか意識することができません。
しかし、特に政治家はこの国家観を持つべきではないか。それが政治家にとって一番重要な部分ではないかと筆者は考えています。
かつての自民党の総裁選では、高市早苗氏だけが国家観を明確に語りました。
岸田文雄前首相は決断力やリーダーシップに欠けるといわれ、そんなことはないと反論しました。しかしこれは個人の能力の話であって、国家観ではありません。
河野太郎氏は思想的に反原発ですが、総裁選になったら批判を恐れて封印しました。これも国家観の話ではありません。単なる利害調整の話であって、風向きが変われば主張がコロコロ変わるのです。
これが国家観のない政治家の特徴です。
それに比べると高市氏は、日本とはどういう国であって、どういう歴史があり、どういう国を目指すのか、そういうことを語りました。こういう人はぶれないのです。
日本にとって本当に大事だと思うことをぶれずにやり遂げようとするのです。左翼の感情的な批判にも負けないでしょう。
こうして見ると、国家観のない他の人たちはとても薄っぺらい話をしていたのではないでしょうか。
今回は、政治家にとって国家観がとても重要なのだという話をしました。
【関連書籍】
◆『よくわかる勝共理論~日本と世界の平和のために~』(光言社)