日本人のこころ 65
尾崎放哉『咳をしても一人』
2022.08.07 17:00
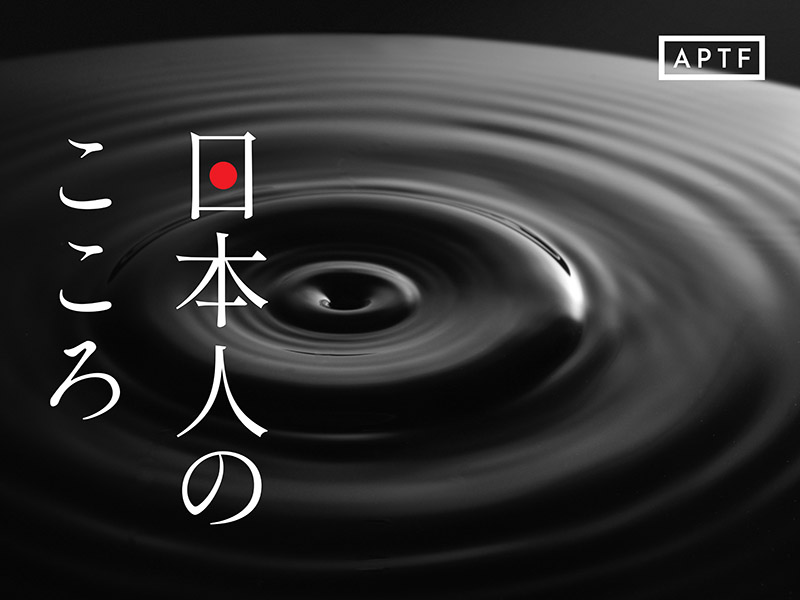
日本人のこころ 65
尾崎放哉『咳をしても一人』
ジャーナリスト 高嶋 久
終焉の地は小豆島
山頭火と並び自由律の俳句を代表するのが尾崎放哉(ほうさい)です。東京帝大法学部卒の詩才あふれるエリートなのに、酒癖の悪さから職を失い、晩年は各所を流浪、終焉の地に選んだのが小豆島でした。小豆島霊場五十八番札所西光寺の南郷(みなんご)庵に居つき、最後の8か月を過ごし、近隣の人たちに世話され、静かに息を引き取ります。
平成6年、「放哉」南郷庵友の会と当時の土庄町長・塩本淳平らの尽力により、終焉の地に南郷庵を復元し、尾崎放哉記念館が開設されました。今は町が管理し、一高時代の師荻原井泉水(せいせんすい)の遺族からの寄贈品や貴重な資料が展示公開されています。
放哉は明治18年、鳥取市の生まれで、本名は尾崎秀雄。父は地方裁判所の書記で、14歳から俳句や短歌を作り始めます。17歳で上京、一高で一学年上で後に自由律俳句運動の指導者となる荻原井泉水に出会います。
20歳で東大法学部に入学した放哉は、『ホトトギス』や新聞に投句した俳句が掲載されるようになります。卒業後、通信社に入りますが、1か月で退職して鎌倉の禅寺に通い、26歳で東洋生命保険(現、朝日生命)に就職して出世コースを進み、郷里の遠縁の娘と結婚。井泉水が創刊した句誌『層雲』に山頭火と並んで句が掲載されるようになります。
この頃の句は「ふとん積みあげて朝を掃き出す」「夫婦でくしゃみして笑った」など。
しかし、人間関係に疲れ、酒癖での失敗もあり36歳で退職します。その後、学生時代の友人の紹介で朝鮮火災海上保険の支配人になり、京城に赴任しますが、酒で失敗し1年で免職。妻にも離縁されます。当時の句は「オンドル冷ゆる朝あけの電話鳴るかな」「石に腰かけて冷え行くよ背骨」など。
一燈園に入って修行
全てを失った放哉は大正12年、京都で西田天香が創始した宗教的な生活共同体・一燈園に入り、托鉢、労働奉仕、読経の日々を送るようになります。当時、ベストセラーになった天香の『懺悔の生活』を読んで感銘し、一燈園での修行で立ち直りを果たそうと、天香に手紙を書き、入園を許されたのです。
入園希望者に天香が決まって聞いたのは「すべて捨てられますか」でした。当時は倉田百三はじめそうそうたる人物が一燈園に入っています。明治維新から50年を経て、西洋へのあこがれにも限界を感じた人たちは、日本文化に回帰し、日本人らしい生き方を求めるようになっていたのでしょう。
しかし、肉体の限界から約半年後、放哉は一燈園を去り、知恩院塔頭の常称院の寺男になり、そこを追い出されると、神戸の須磨寺に身を置きます。この頃の句は「障子しめきつて淋しさをみたす」「こんなよい月を一人で見て寝る」など。
海の見える所で死にたい
その後、放哉は、関東大震災で妻子を失い、京都で一人暮らしの井泉水の元に身を寄せます。老いを感じた放哉は、井泉水に「海の見える所で死にたい」と訴え、井泉水は遍路巡礼で知り合った小豆島の句友に、海辺の庵を探して欲しいと依頼。その紹介で、放哉は大正14年に島へ渡り、西光寺の南郷庵に住み込みます。終(つい)の棲家となった家で、「人の親切に泣かされ今夜から一人で寝る」と詠んでいます。

大正15年、41歳の放哉は肺結核で亡くなります。世話をしていた隣家の老婆に看取られての最期でした。辞世の句は「春の山のうしろから烟(けむり)が出だした」。
小豆島での8か月で生まれた句が「咳をしても一人」「障子あけて置く海も暮れ切る」「足のうら洗へば白くなる」など。あの時代より豊かになったはずの日本で、放哉の孤独が心に迫ります。
小豆島には、空海が生誕地の讃岐と京都を往復する際、しばしば立ち寄り、各所で修行や祈念を行ったことから、小豆島八十八ヶ所霊場が設けられています。約2週間で歩いて回れ、四国八十八ヶ所よりも回りやすいことから、年間約3万人が訪れるようになりました。それに伴い、お遍路さんを接待する文化が育まれたのです。放哉も、その恩恵を受けたことになります。
放哉のファンは全国に多く、命日にあたる4月7日、西光寺で「放哉忌」が営まれています。一人の孤独を極め、体の底から湧き上がってくる思いを、短い言葉に表したことで、放哉は時代を超え人々に愛されるようになったのです。文学が生まれくる、ひとつの典型と言えるでしょう。



