日本人のこころ 56
鴨長明『方丈記』
2021.11.07 17:00
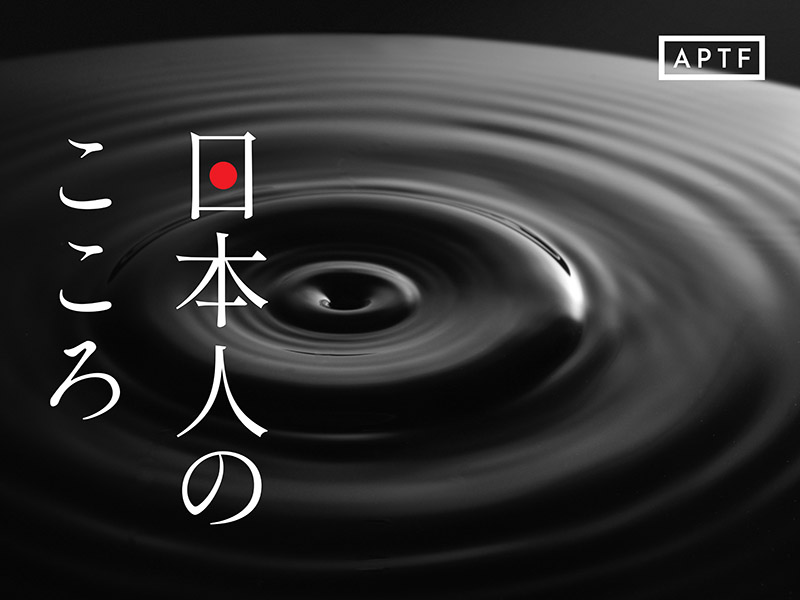
日本人のこころ 56
鴨長明『方丈記』
ジャーナリスト 高嶋 久
ゆく川の流れは絶えずして…
「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」という始まりの『方丈記』は、学校の古典の授業で読んだことがあるでしょう。鎌倉時代に書かれた随筆で、『枕草子』『徒然草』と共に日本三大随筆とされています。東日本大震災の時に注目されたのは、当時の災害の様子を、災害ルポのように細かく描写していたからです。
日本は自然に恵まれている半面、自然災害も多い国で、人間を超えた大きな力には感謝し、畏れるしかないと人々は思っていたのでしょう。今回のコロナ禍でも、日本政府は他国のようにロックダウンをすることはできず、ただ国民に「お願い」するしかありませんでした。それは今に始まったことではなく、もっと政府が権力をもっていたような古代にも同じで、そうなったのは自然災害が多かったからです。
冒頭の、川の流れが同じでないというのは、近代的な堤防のなかった時代、洪水が起こると川は流れを変えてしまったからではないかと思います。鴨長明が毎日のように目にしていた鴨川にしても、今よりはるか広い範囲で流れを変えていました。その川の流れを人の世にたとえ、仏教の無常観を淡々と描きながら、最後には達観したような人生観に到達したのが、今の世にも読み継がれている理由でしょう。
鴨長明は、下鴨神社の摂社である河合神社の神官の次男として生まれました。才能に恵まれ、随筆家に歌人、音楽家、そして建築家と多彩な顔を持ち、後鳥羽院の寵愛を受け『新古今和歌集』の編纂にも携わります。その際の歌合わせでは、藤原定家と競って四戦無敗だったほど、若い長明は前途有望だったのです。

ところが父が亡くなると、後ろ盾を失った長明は後継としての道を断たれ、出世の道から遠ざけられてしまいます。和歌の名人としても名高かった鴨長明は、その後、歌人として何とか生計を立てますが、楽なものではありませんでした。さらに当時は天災や人災が繰り返し起こり、仏教がいう末世のような時代でした。
神官になる道を絶たれた長明は出家し、東山や大原、日野で隠遁生活を送ります。『新古今和歌集』に「石川や瀬見の小川の清ければ 月も流れをたずねてやすむ」をはじめ十首が選ばれていますので、和歌を通じてかろうじて上流社会とのつながりを保っていたのです。
30歳を過ぎたころ、長明は妻子を残して、祖母の家を追い出されます。家付きの嫁に三下り半を突き付けられたのでしょう。
1211年には、鎌倉幕府三代将軍源実朝の和歌の師として鎌倉へ下向します。その折、源頼朝の法華堂(源頼朝の墓所)を参拝した長明は「草も木もなびきし秋の霜消えて 空しき苔をはらう山風」と詠んでいます。しかし、期待した和歌の師範にはなることができず、そのむなしさが『方丈記』の執筆の動機であったともいわれています。
一人で生きる覚悟
翌年、京に帰って『方丈記』を完成させ、4年後の1216年に62歳で亡くなります。自分のついてなさを、「すべて、あられぬ世を念じ過しつつ、心を悩ませること、30余年なり。その間、おりおりのたがいめに、おのずから、短き運をさとりぬ。」と書いています。
出家した長明は「すなわち、50の春を迎えて、家を出て、世を背けり。もとより妻子なければ、捨てがたきよすがもなし。」(方丈記27段)との心境になります。家族に恵まれ、充実した人生を送ったとしても、最後には一人で死んでいかなければなりません。最愛の伴侶がいても、いつかは別れることになります。それは生きている限り仕方ないことで、一人で生きる覚悟をすることです。
最後に日野の山中に庵を結んだ長明は「ここに、六十の露消えがたに及びて、さらに、末葉の宿りを結べる事あり。いわば、旅人の一夜の宿を造り、老いたる蚕の繭を営むがごとし。これを中ごろの栖(すみか)に並ぶれば、また、百分の一に及ばず。」と記しています。
終の棲家として設けた方丈が河合神社に再現されています。移動に便利な組立式で、広さが一丈(約3メートル)四方であることから「方丈」と呼ばれています。昔の家の100分の1の大きさしかありませんが、一人暮らしの長明にとって格好の住処だったのでしょう。その暮らしから、一人での生き方を探究するようになります。
長明の庵の近くには山の番人の小屋があり、男の子がいました。長明になついていたので、良寛さんのように二人でよく遊んでいました。
「かれは十歳、これは六十。その齢ことのほかなれど、心をなぐさむること、これ同じ。或は茅花(つばな)を抜き、岩梨(いわなし)を採り、零余子(ぬかご)を盛り、芹を摘む。或はすそわの田居にいたりて、落穂を拾ひて穂組をつくる。」
身近な自然を親しみながら、煩わしい人間関係から離れ、気の合う人とだけ付き合う。それが晩年の好ましい暮らし方かもしれません。



