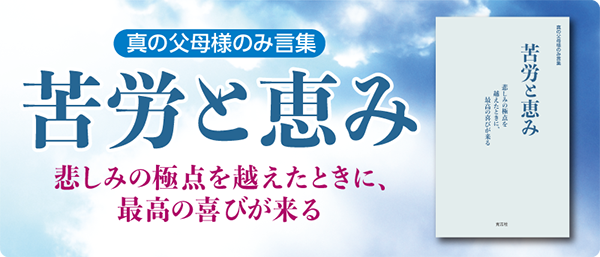週刊ブレラ 20
お盆を故郷で過ごす
2025.08.18 17:00

週刊ブレラ 20
お盆を故郷で過ごす
編集部
8月お盆の時期、戦後80年の「終戦の日」を故郷で過ごされたかたも多いことでしょう。
大雨などの被害に見舞われた地域の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
ところで、改めて「お盆」とは何でしょう?
AIに聞いてみました。
「お盆が8月に行われるのは、明治時代に新暦が導入された際、旧暦7月15日のお盆を農繁期と重ならないように、約1カ月遅らせて8月15日頃に行うようになったためです。これを『月遅れ盆』といいます。
お盆は、ご先祖さまの霊を祀(まつ)り、感謝を伝える大切な行事です。旧暦では7月15日頃に行われていましたが、明治時代に新暦が導入された際に、農作業の都合などで7月15日では都合が悪いため、8月15日を基準とする地域が増えました。これが現在の8月のお盆の由来です」
お盆の時期の帰省は、必然的に実家の親・兄弟や故郷の親戚との再会を果たすとともに、あの世のご先祖さまをこの世にお迎えするための帰郷ともなるわけです。
そしてご先祖さまあっての家族であり、親戚であることを自覚する機会でもあります。
コロナ禍は社会における集いや交流に多大な影響を与えました。特に葬祭の簡易化や縮小化が進みました。それに伴い、親族との交流の機会も減りました。
また、日本社会の少子高齢化は、とりわけ地方の社会(共同体)の在り方に大きな変化をもたらしています。
「還故郷」「氏族メシヤ」は、とりわけ1990年代以降、常に復帰摂理の中心テーマとなってきました。
祝福家庭にとって「宿命の道」ともいわれるのが、神氏族メシヤの責任を果たすことであり、故郷に天の父母様(神様)を迎えることです。
しかし頭では分かっていてもお盆や年末年始、連休の“プチ還故郷”で責任を果たせるような簡単なものではありません。
筆者の故郷は消滅可能性の高い自治体の一つです。
帰省するたびに、人口減少、超高齢社会の波に浸されていっているのを目の当たりにします。
地上での時間(肉身生活)は期限付きです。無限ではありません。
還故郷どころか、故郷そのものが失われてしまうかもしれません。
氏族メシヤはどこにやって来て、どこに地上天国をつくらなければならないのか。
国家もまた、故郷の集合体。
戦後80年の節目を迎えて、故郷の未来は国の未来であり、国の未来は故郷の未来であることを実感します。
急がば回れ。千里の道も一歩から。
親族の一人一人に対して「ために生きる」実践をするところから始まるのだと、肝に銘じる「終戦の日」の誓いとなりました。
暑さはまだまだ続きそうです。
ミッション完遂も、健康あっての物種(ものだね)。
読者の皆さま、どうぞご自愛ください。

Blessed Life(ブレラ)編集部は、皆さまの情報ライフをもっと豊かにするために、これからも精進してまいります!
読者の皆さまの「ブレラ、こんなふうに活用してるよ~」「ブレラにこんな記事あったらいいな~」といった声、お待ちしております。
ご感想やご意見・ご要望、お気軽にお寄せください!