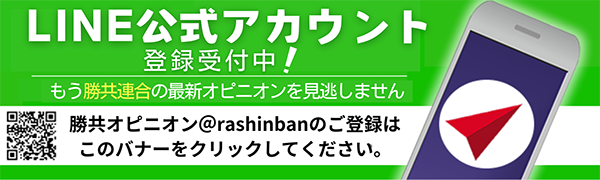共産主義の新しいカタチ 86
労働価値説とかけ離れた「オープンソース」の発想
2025.11.12 17:00
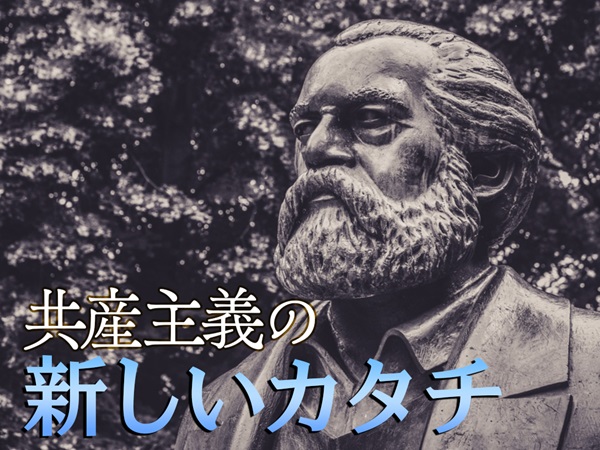
共産主義の新しいカタチ 86
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
テクスト論とオープンソースの衝撃
ロラン・バルト(下)①

ロラン・バルトはエクリチュール(言葉遣い)と「作者の死」について、「テクストは様々な文化的出自をもつ多様なエクリチュールによって構成されている。そのエクリチュールたちは対話を交わし、模倣し合い、いがみ合う。しかし、この多様性が収斂する場がある。その場とは、これまで信じられてきたように作者ではない。読者である。(略)テクストの統一性はその起源にではなく、その宛先のうちにある。(略)読者の誕生は作者の死によって購われなければならない」(「作者の死」)と述べました。
このバルトの「テクストの生成」と「作者の死」の考え方は、書物や芸術作品など「作者により生まれたもの」が、「読み手や鑑賞者によって編み上げられるテクスチャ(織り物)」と見なす考え方で、一種の「存在=生成論」と見なせますが、これを、内田樹氏が「オープンソース」としてのリナックス登場の背景について説明しており、一部紹介しました(『寝ながら学べる構造主義』)。
冒頭のバルトの記述は、ほとんどそのままインターネット・テクストに当てはめられるとし、リナックスという「オープンソース」の登場の衝撃について「音楽や図像についてコピーライト(著作権)の死守を主張している人たちがいますが、その人たちもむしろ自分の作品が繰り返しコピーされ、享受されること(前回述べたようにベリオの作品がマーラーの交響曲をそのまま引用した例など)を『誇り』に思うべきであり、それ以上の金銭的なリターンを望むべきではない、という新しい発想に私たちはしだいになじみつつある」とバルトの思想と内田樹氏は重ね合わせます(『寝ながら学べる構造主義』)。
ところが、バルトのテクスト論は確かにそうかもしれませんが、あえて言うならばむしろマルクス主義の労働価値説と最もかけ離れているものこそ、「オープンソース」の発想なのです。
このオープンソースのオペレーティング・システム(OS)のうち、特にリナックス(Linux)は元々、フィンランドのリーナス・トーバルズ氏が「誰でも参加でき自由に改造できるOS」を提唱し、世界中のコンピュータオタクが参加し驚くべき進化を遂げました。
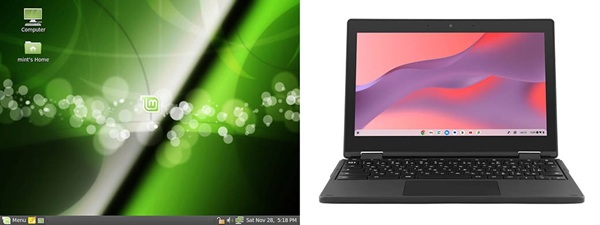
アップルのパソコンMac搭載のMac OSと同じUNIX(ユニックス)系といわれるOSです。特に最近では、グーグルの開発したChrome OSを搭載した「クロームブック」はCMでも知られ、ウィンドウズ搭載のパソコンより低スペックですが手頃な値段で手に入る機種としてかなり浸透してきました。このChrome OSもリナックスベースのOSです。
また、スマートフォン業界では、アップルiPhoneと2分するのが「アンドロイドOS」機種で、このアンドロイドもリナックスの一種です。つまりスマートフォン界ではUNIX系がデファクトスタンダードなのです。
(続く)
★「思想新聞」2025年11月1日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅