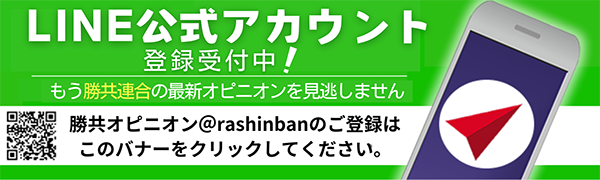共産主義の新しいカタチ 85
著作権に対するロラン・バルトの考え
2025.10.29 17:00
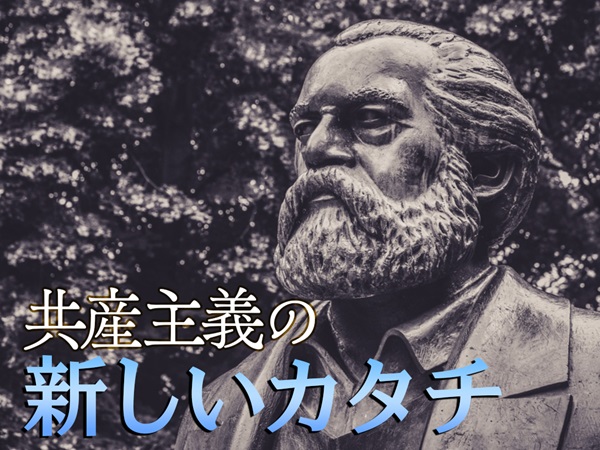
共産主義の新しいカタチ 85
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
スターリン戦争の欺瞞冷笑するバルトーク
ロラン・バルト(中)③

テクストの生成と作者の死の意味
前回の後半で触れたこのような「著作権をめぐる問い」に対して一つの解釈を与えるのが、バルトの「テクストの生成」と「作者の死」の考え方です。
そこでは、書物や文書、芸術作品など「作者によって書かれたもの」とは、「読み手(ないしは鑑賞者)によって編み上げられるテクスチャ(織り物)にほかならない」と見なす立場で、一種の「存在=生成論」と見なしてよいと思われます。
こうした立場は、例えばハイデガーやフッサールの現象学、西田幾多郎といった思想にも通じる世界があると指摘できましょう。
これを、内田樹氏が「オープンソース」としてのリナックス登場の背景を説明しています(『寝ながら学べる構造主義』)。
◇
インターネット上でのテクストや音楽や図像の著作権についていろいろな議論が展開していますが、バルトは今から40年前に、既に「コピーライト」というものを原理的に否定する立場を明らかにしています。
作品の起源に「作者」がいて、その人には何か「言いたいこと」があって、それが物語や映像やタブローや音楽を「媒介」にして、読者や鑑賞者に「伝達」される、という単線的な図式そのものをバルトは否定しました。…「コピーライト」あるいは「オーサシップ」という概念は、その文化的生産物が「単一の産出者」を持つ、という前提がないと成り立ちません。「作者」とは、何かを「ゼロ」から創造した人です。聖書的な伝統に涵養(かんよう)されたヨーロッパ文化において、それは「造物主」を模した概念です。誰かが「無からの創造」を成し遂げた。そうであるなら、創造されたものはまるごと造物主の「所有物」である。そう考えるのはごく自然なことです。
近代までの批評はこのような神学的信憑(しんぴょう)の上に成立していました。つまり、作者は作品を「無から創造」した造物主である、と。
★「思想新聞」2025年10月1日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅