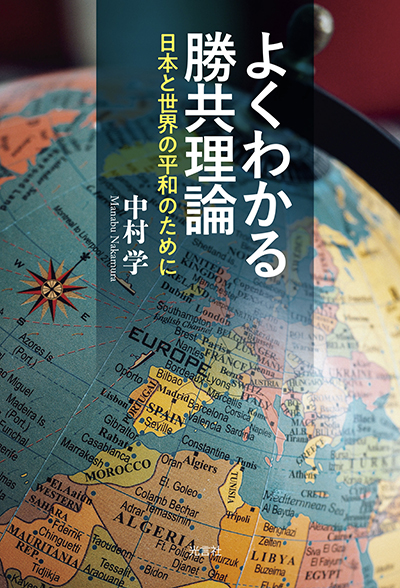ほぼ5分で読める勝共理論 99
「夫婦別姓」に反対する理由
2025.10.16 12:00

ほぼ5分で読める勝共理論 99
夫婦別姓問題②
「夫婦別姓」に反対する理由
編集部編
「夫婦別姓を認めないことは憲法違反ではない」
今回は、なぜ私たちが夫婦別姓に反対するのか、その理由についてお伝えします。
勝共連合は選択的夫婦別姓、つまり全員の名字を別にするのではなくて、変えたい人だけ変えるという制度に対しても反対しています。
その理由は、ファミリーネームが日本からなくなってしまうからです。
今から10年前、夫婦別姓を認めないことは憲法違反ではないか、ということが最高裁で争われたことがありました。
その時最高裁は、「名字は個人の名称であると同時に、家族の名称でもある」と言いました。
つまり「名字は家族の名称でもあるから、個人の都合では変えられない」と言ったのです。
それで「夫婦別姓を認めないことは、憲法違反ではない」という判決を出しました。
この判決は勝共の観点でも高く評価できると思います。
この部分がとても大事なので、詳しく説明しましょう。
例えば、今の日本の制度では、佐藤さんという人の名字はその人だけの名前ではありません。佐藤さんの奥さんや子供、家族みんなの名前でもあります。
佐藤さんという家族の名前に太郎君とか花子さんという個人の名前が付くようになっています。
では、選択的夫婦別姓が認められたらこれがどうなるでしょうか。
佐藤さんと鈴木さんが結婚すると、鈴木さんは「佐藤」と名乗ってもよいし、「鈴木」のままでも構わないということになります。
そうすると、「佐藤」という名字は家族全体のものではなくなるわけです。「佐藤」もその人個人の名前ということになります。
つまり「佐藤太郎」という名前全部が個人の名前になるということです。これは夫婦別姓を選んだ人だけではなく、選ばなかった人も同様となります。従って、選択的夫婦別姓制度にすると日本人の名字は全て個人の名前になります。
これが「ファミリーネームがなくなる」という意味なのです。
このことが「選択的夫婦別姓」にも反対する最大の理由です。
子供の福祉という問題はどうなるのか?
選択的夫婦別姓というのは、単に個人を尊重する制度ではないということです。そうではなく、日本全体からファミリーネームをなくしてしまう、法律的に言えば戸籍制度を根本から変えてしまう、革命のような内容なのです。
では、ファミリーネームが消えたらどうなるでしょうか。
その最大の被害者は子供です。夫婦別姓は親子別姓になることも意味します。親子別姓になったら親子の一体感は薄れないでしょうか。
そんなことでは薄れないと言う人もいるでしょう。しかし先ほど紹介した最高裁判決は、「親子が同じ名字であることには子供の福祉のために意味がある」と言いました。
これが最高裁の判断です。
また、夫婦別姓になるなら子供の名字をどちらにするか決めないといけなくなります。その時に夫婦がもめることはないのでしょうか。
そもそも夫婦別姓で裁判を起こして争う人たちは、自分の名字にかなり執着がある人たちなのです。
その人たちが子供の名字を夫か妻かどちらかに決めるときに、いつも円満に決められるものなのでしょうか。「あなたの名字でいいですよ。私は譲りますよ」と、すんなり言うでしょうか。
そうは思えません。
さらに言うと、親子別姓は兄弟別姓になることも意味するのです。
夫婦では自分たちがお互いに納得して別姓を名乗るのでしょうが、子供も親と違う名字になる、あるいは兄弟とも違う名字になるということです。
子供にとっては自分で選んだ名字ではありません。家族みんなの名字がバラバラになって、それで家族の絆には全く問題がないのだと言えるのでしょうか。
LGBT問題でも同様ですが、家族制度を変えようとする人たちは、子供の福祉という問題には全く触れないのです。
触れたとしても、子供は親の都合を理解してくれるはずだから大丈夫だと言って決めつけてしまうのです。
親が事情を話せば子供は受け入れるしかありません。離婚をするときもそうです。子供が受け入れたからといって、本当にその子が親の事情を全て理解しているとは限りません。
大人の都合を子供に押し付けているとしか思えないのです。
改めて結論を言いますが、選択的夫婦別姓は日本の家族制度を壊すことを意味しています。
それが子供の福祉にとってどの程度の影響があるかということは、やってみないと分かりません。どれだけ家族がバラバラになって、どれだけ子供が傷つくのか。あるいは虐待のような問題がどれくらい増えるのかといったことはやってみないと分からないことです。
そんな重大な問題を「自分らしさ」のためといって、子供のことまで考えずに一方的に主張する。それが選択的夫婦別姓問題なのです。
【関連書籍】
◆『よくわかる勝共理論~日本と世界の平和のために~』(光言社)