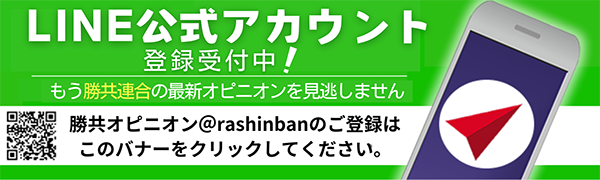共産主義の新しいカタチ 83
ハンガリーの作曲家バルトークのエピソード
2025.10.15 17:00
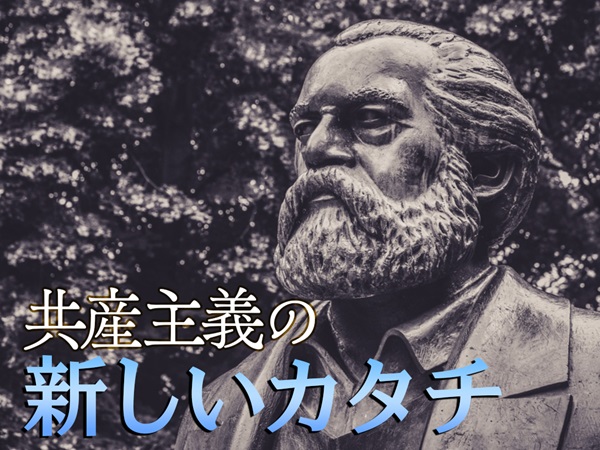
共産主義の新しいカタチ 83
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
スターリン戦争の欺瞞冷笑するバルトーク
ロラン・バルト(中)①

ロラン・バルトはソシュールの記号学(論)を敷衍(ふえん/おし広げること)・駆使した構造主義哲学者ですが、当初は文芸批評家として知られました。ここで記号論での「術語」を確認すると、「ラング」は母国語のこと、「スティル」とは「スタイル」、「エクリチュール」とは「言葉遣い」ですが、内田樹氏は「エクリチュールとスティルは違います。スティルはあくまで個人的な好みですが、エクリチュールは、集団的に選択され、実践される《好み》」と解説(『寝ながら学べる構造主義』)。
バルトはマルクス主義における文化・芸術上の理念である「社会主義リアリズム」とは異なる形での「革命的なアンガージュマン(社会参加)のエクリチュール」を模索するのですが、その一方「作者(著作権)の死」をも主張することになります。
つまり文学作品などは作者の手を離れれば、生成する「テクスト(織物)」という考え方です。そこで引用などの概念も改めることになります。
バルトークのオケコンとショスタコーヴィチ
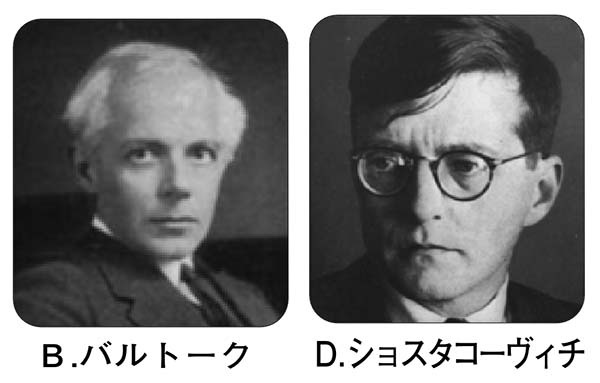
ここで想起したいのが、ハンガリーの作曲家ベラ・バルトークのエピソードです。バルトークはブダペスト音楽院教授からナチス台頭後、米国に亡命します。
米国で貧窮に喘いでいたバルトークを助けたいと、指揮者S・クーセヴィツキーは、手兵ボストン交響楽団のために委嘱した作品が、今日「オケコン」として広く知られる「管弦楽のための協奏曲」です。
しかし白血病に冒されたバルトークは曲の完成・初演しほどなく他界(1945)。このバルトークの傑作で諧謔(かいぎゃく)的に引用されるのが、ソ連の「体制派作曲家」、D・ショスタコーヴィチの交響曲第7番です。
ソ連と親和性が高かったF・ルーズベルト米政権では、レニングラードをナチスの手から守った《大祖国戦争》を描いたとされるこの曲は、トスカニーニやストコフスキーら名指揮者により、70分強の大作ながら頻繁に演奏。第5交響曲でソ連政府に「社会主義リアリズム」を体現した作品とされ、「ソ連を代表する作曲家」を確立したショスタコーヴィチでした。
しかし、米国内の「ソ連=正義」という空気一色にもかかわらず、バルトークは冷やかに見ていました。なぜならナチスの侵略から祖国を守ったはずのソ連は、バルト三国やポーランド、ルーマニア、フィンランドなどをドイツと分割しようとしたのです。
つまり「祖国を侵略から守る戦争」とは全くソ連のプロパガンダに過ぎませんでした。ハンガリーも元々、ロシアやトルコといった大国の脅威にさらされてきたのです。「祖国防衛戦」を謳ったともてはやす米国を、バルトークは壮大な茶番に映り、自作品の中で「小国の悲哀(エレジー)」と並べて配置しシニカルに批判したといえましょう。
バルトークは戦後のヤルタ体制の下で辛酸を嘗(な)めた祖国の運命をもはからずも「予言」したことになるかもしれません(戦後東欧圏に組み込まれ、民主化を求めたもののソ連軍によって武力鎮圧されます〔「ハンガリー動乱」〕)。
(続く)
★「思想新聞」2025年10月1日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅