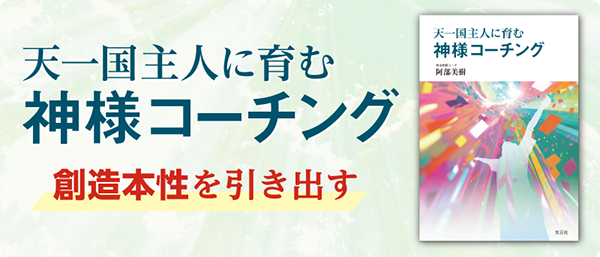ダーウィニズムを超えて 126
普遍論争について
2025.08.31 22:00
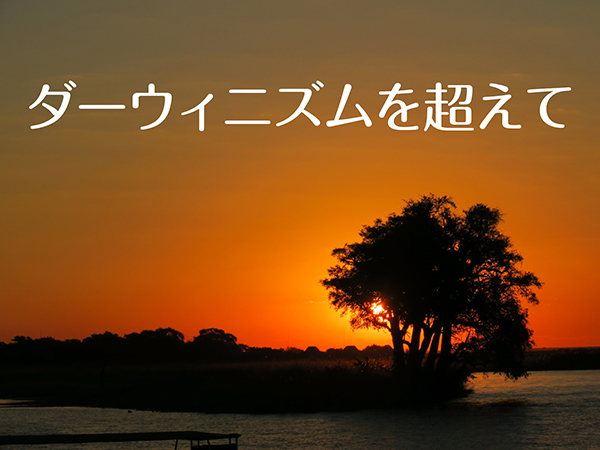
ダーウィニズムを超えて 126
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「ダーウィニズムを超えて」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。
生物学にとどまらず、社会問題、政治問題などさまざまな分野に大きな影響を与えてきた進化論。現代の自然科学も、神の創造や目的論を排除することによって混迷を深めています。
そんな科学時代に新しい神観を提示し、科学の統一を目指します。
統一思想研究院 小山田秀生・監修/大谷明史・著
第九章 科学時代の新しい神観
(二)統一思想による新しい神観
(3)普遍と個物の統一
1. 普遍論争について
中世のスコラ哲学における一大論争となったのが、普遍は実在するか否かに関するいわゆる普遍論争であった。スコラ哲学の初期には「普遍は個物に先立ってある」という、プラトン的な実在論が優勢であった。スコトゥス・エリウゲナ(Eriugena, ca.810~877)やアンセルムス(Anselmus, 1033~1109)がその代表であった。ところが、それに対してロスケリヌス(Roscellinus, ca.1050~1120)が「普遍は個物の後にある」という唯名論を唱えた。個々の事物のみが真の実在であって、普遍はわれわれの作り出した単なる抽象物、単なる名にすぎないというのである。かくして実在論と唯名論が対立することになった。
その後、この二つの立場を調停する、アリストテレス的実在論と呼ばれる第三の立場が生まれた。プラトンは普遍的なイデアが真の実在であるとしたが、アリストテレスによれば、個物が第一実体であり、本来的な意味での存在者である。普遍は第二実体であり、個物の形相としてあるとした。アベラルドゥス(Abaelardus, 1079~1142)は、普遍はまず神のうちにあり、次に個物のうちに共通の本質的規定としてあり、そして人間の悟性のうちに、思惟の結果、得られた概念としてあると考えた。トマス・アクィナス(Thomas Aquinas, 1225~1274)はアベラルドゥスと同様に、普遍は神のなかにあり、それを原型として神は世界を創造したと考えた。そして個物のなかの形相は普遍的なものであるから、個物がまさに個物になるのは資料によるとして、アリストテレスと同様に、「資料が個別化の原理である」と主張した。アリストテレス的実在論の立場は「普遍は個物のうちにその形相としてある」というものであった。
それに対してドゥンス・スコトゥス(Duns Scotus, 1266/74~1308)は、個物をして個物たらしめるものは質料ではなくて、個物の中にある個体形相であると主張した。彼は、アリストテレスの実在論の立場に立ちながら、個体性を重視し、唯名論的立場に近づこうとするものであった。
後期のスコラ哲学において、ウィリアム・オッカム(William Occam, ca.1280~1349)は唯名論の立場を明確に打ち出した。すなわち真に実在するのはただ個物のみであり、普遍とは多くの事物、つまり個物の集合を現す記号または名にすぎないというのである。オッカムは神の中にあるのは普遍ではなくて、個物のイメージであると考えた。
唯名論の立場は、抽象的、思弁的な思想に対して、直観的な知識、経験的知識を重んじることに通じていた。オッカム以後、唯名論の立場が支配的になっていった。それとともに、知識と信仰の分離が進んでいくことになった。それはスコラ哲学の崩壊と近世の哲学の誕生を告げるものであった。
近世において、唯名論は個々の事実と特殊に重きを置くイギリスの経験論へと流れていった。一方、スコラ哲学の伝統であった実在論は、理性や法則の普遍性を重んじるパースの哲学、および数理や論理性を重んじる論理実証主義として現れてくるのであった。
---
次回は、「現代の生物学の立場」をお届けします。
◆『ダーウィニズムを超えて』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ