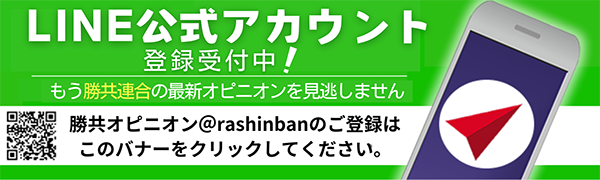共産主義の新しいカタチ 70
イデオロギーとして肥大化していった記号学
2025.07.02 17:00
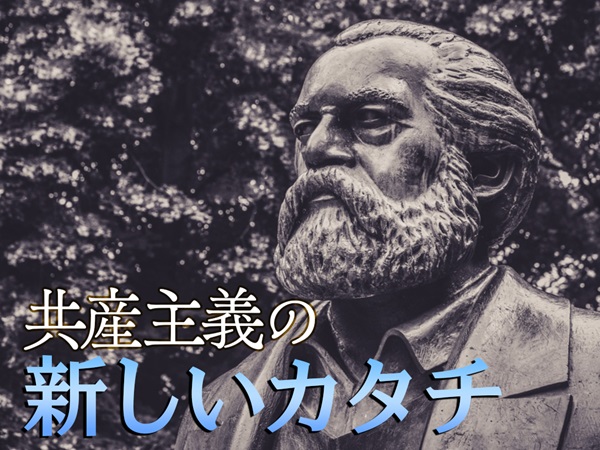
共産主義の新しいカタチ 70
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
「記号学」から「構造主義」へ
C・ヤコブソン とC・パース➁
母語に誇りをもつアイデンティティー
さて、ソシュール思想に関して、「ラングの専制」という内容を先述しました。後の記号論における中心的な役割を果たしたフランスの構造主義哲学者ロラン・バルトが、その「課題」を引き継いだのです。
そもそもフランスは、母国語に対する誇りと愛着が人一倍強く、フランス語がフランス人としてのアイデンティティーの主要素となっているほどです。
このため、同じフランス語を使いながら、フランス人として生きるよりスイス人としての誇りを貫いたソシュールと、厳格でより美しいフランス語を使いこなすことが求められたフランス人のロラン・バルトとの出自的背景の違い、つまり、厳格なフランス人としてのアイデンティティーを求められたバルトの方が、より「ラングの専制」を身をもって実感したということなのです。
反体制のイデオロギーとして肥大化
ここで現在の言語をめぐる考え方を見てみましょう。例えば日本では文科省の国語審議会が、「日本語の乱れ」について指摘すれば、時折報道されますが、多民族国家フランスの場合は日本よりもっとセンシティブで「言葉の乱れ」には今日でも非常に敏感です。いいか悪いかはともかく、「標準語」ないしは「スタンダードな国語」というものが存在しています。
そうした状況が例えば、「専制」という強い表現はともかく、「ラング=国語」が「支配」(広く遍く通用しているという意味で)していることがなければ、つまり「標準」が示されなければ、例えば「国語」という試験科目などは成り立たなくなります。これをよく考えると、「スタンダード」を「支配」と捉えれば、教育は成り立たず、したがって言語の混乱、すなわち『旧約聖書』創世記の「バベルの塔」の物語が現実のものとなるのです。
そう考えれば、「ラングの専制」に対する果敢な「抵抗」というものは、結局のところ何を意味するでしょうか。紛れもなく「言語破壊」ということになるでしょう。
標準語としての「ラング」を含む言語とは、そもそも「自分以外の他者とコミュニケーションできてなんぼ」のものなのです。その「専制」に抵抗したからといって、「他人に分からない言葉」を発したり、「他人に分からない文字」を書き連ねたりすることは、まさに独我論の世界であり、周囲からは狂人や変人扱いされるでしょう(他者に理解されることなしに自己顕示すらできないのです)。
一部、諜報機関など、組織内部しか分からない言葉や文字(並び)を扱う場合もありますが、大多数の一般人には関係のない話です。
こうした言葉の本義からすれば、「専制を超克できない」と言って悩む方がむしろ狂っている、あるいは病んでいると言うべきでしょう。本当にそうしたいのであれば、ほとんど解読できないインカ文字やマヤ文字などで書き記すか、自分だけの文字を「発明」し、それを信奉者に流布すればいいだけの話です。
つまるところ、ことほどさようにロラン・バルトに至って記号学はますますイデオロギー的に肥大化していった、と見なさざるをえません。
米哲学者パースも独自の記号論提唱
さて、ヤコブソンですが、いわゆる「記号論」ではソシュールの影響ばかりではなく、プラグマティズムの創始者でもある米国の哲学者チャールズ・S・パース(1839〜1914)が独自に展開した「記号論」をも高く評価し、影響を受けています。パースの記号論は、「人間の認識は記号過程」というもので、思考とは、まず何かを指し示す記号が現れ、それを別の何かを示す記号に変換する過程と捉え、「全ての存在は記号である」とする独自の実在論的な世界観を開陳しています。
このほか、ヤコブソンらと共に「プラハ言語学サークル」に参画した「ソシュール直系の言語学者」とも言えるエミール・バンヴェニストや、この「プラハ派」による「音韻論」に対抗して、デンマークにおいて「言語素論」を展開するなど独自にソシュールの記号言語学の可能性を模索した「コペンハーゲン言語学サークル」のルイ・イェルムスレウなども「記号論」の系譜に連なり、ロラン・バルトに影響を与えました。
★「思想新聞」2025年6月1日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「天安門事件から36年~日米同盟の危機」2025年 6月4日 中野駅