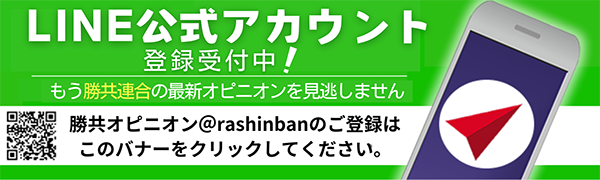共産主義の新しいカタチ 69
記号学と言語学のその後の展開
2025.06.25 17:00
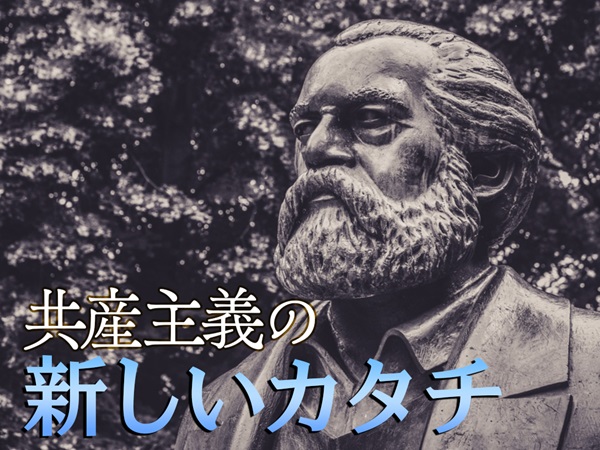
共産主義の新しいカタチ 69
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
「記号学」から「構造主義」へ
C・ヤコブソン とC・パース①
ヤコブソンと「プラハ言語学サークル」
ソシュールの手を離れた記号学の体系は、大まかな構造主義的潮流として現代思想に流入していきます。しかしバルトを中心とした「ラングの専制」という「反権力へのイデオロギー」は、マルクス主義に飽き足らぬ知識層へと染み渡っていったのです。それがポストモダン思想がもてはやされたゆえんです。
ソシュールの打ち立てた「記号学」の体系は、かくして主としてフランスを中心とした現代思想に大きな影響を与えました。今回は記号学(記号論)と言語学のその後の展開について見てみることにします。
ソシュールから構造人類学を樹立し「構造主義の父」となったレヴィ=ストロースまでの流れを見ると、この両者を結びつけたのが、若くして革命前夜のモスクワ大学で「モスクワ言語学サークル」を主宰したロマン・ヤコブソンです。

ロシア革命直後の内戦で混乱するソ連を避けハプスブルク=オーストリア帝国から独立して間もないチェコに渡り、今度はプラハで1926年に発足した「プラハ言語学サークル」に、ニコライ・トルベツコイらと共に参加。この「プラハ学派」は、ソシュール言語学・記号学影響の下で、言語の本質は音の弁別性にあるとする「音韻論」を展開し、言語学の新しい地平を切り拓きます。
レヴィ=ストロースとチョムスキー
そしてさらにナチス・ドイツにチェコが併合されるとユダヤ人迫害の手を逃れ1941年、ヤコブソンは米国に渡ります。その米国ニューヨークで亡命学者の受け皿となっていた「高等研究自由学院」に移り、1942年、同じく米国で文化人類学の「修行中」だったレヴィ=ストロースに、ソシュール記号学と音韻論を手ほどきしたのが、ヤコブソンでした。
このヤコブソンはその後ハーバード大学の教授となり、同じロシア系ユダヤ人の言語学者ノーム・チョムスキーを指導し、やがてチョムスキーはヤコブソンのライバルでもあったL・ブルームフィールドにも師事し、いわゆる「生成文法理論」を引っさげて一躍、言語学界の寵児となります。
今日、チョムスキーは学者としてよりも、マイケル・ムーアと共に9・11テロ後の米国の安保政策を批判する急先鋒として知られていますが、もともとベトナム戦争の際にも過激な反戦運動を支持しているほどの「反米」社会主義者であり、近年では学術論文よりも圧倒的に政治論文の方が多いと揶揄されるように、専ら政治活動家のようになっています。
意味と価値において基準となる差異概念
さて、記号学がこうした内容を説くだけのものであれば、それは何も唯物論や言語原子論のようなものとは趣きを全く異にする思想として、別段目くじらを立てる必要もないでしょう。
しかしながら、いかんせん、ソシュールは言語学の領分を遥かに踏み超え、自らの言語学を中核に据えた「普遍的な学問体系としての記号学」の樹立を企図したのです。先にも触れましたが、その上で重要な役割を担ったのが、「差異」の概念とそこから生じてくる「価値」の考え方なのです。
「記号の恣意性」を説いたソシュールの思想体系は、言語のみならず、文化全般というものが、「絶対」「不変」「普遍」「当為」とは対極にある「恣意的なもの」と見なすことで、その文化の持つ様々な意義や価値を解体するよう結果的に仕向けることになりました。それがポストモダン思想に直結するのです。
(続く)
★「思想新聞」2025年6月1日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「天安門事件から36年~日米同盟の危機」2025年 6月4日 中野駅