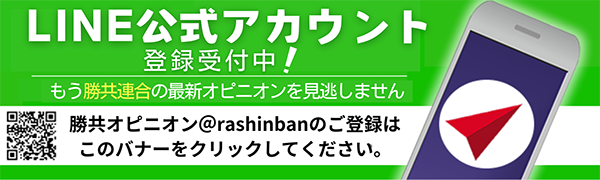共産主義の新しいカタチ 68
要素還元主義とは対極にある絶対的価値
2025.06.18 17:00
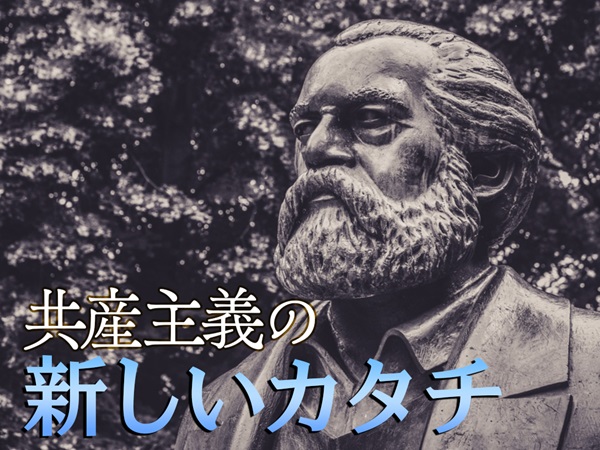
共産主義の新しいカタチ 68
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
文化破壊に繋がる記号の恣意性
フェルディナン・ド・ソシュール(下)③
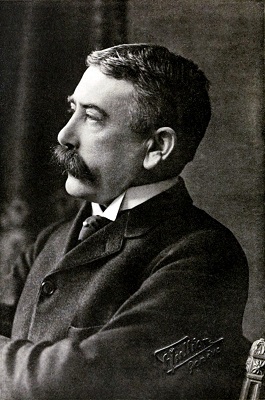
さて、こうした「所有の排他性」(※前回を参照)というものを考えた時、そこに「差異による価値」は果たして生じるのか。「所有の排他性」ないし「排他的価値」とは、換言すれば「交換できないこと」だからです。
例えば、当然のことですが、私たちは両親から生まれました。つまり「子は親を選べない」としばしば言われるように、モノを選んだりするようには家庭環境を選べないわけです。自分の都合のいいように親や子供を取り換えたりできないこと、「取り替えられなさ」「交換できない関係」というものは、世の中に少なからず存在しているのです。
あるものと別のものとは、その「差異」によって価値が決まる、というのがソシュールの考え方でした。しかし、それでは自分の親とか家族といったような「取り換えることのできない存在」「取り換えられない価値を持つ存在」という場合は明らかに当てはまりません。
「所有の排他性」(交換できない価値)という場合、人間関係における「所有」と言えば、「子は親のもの」「親は子のもの」「夫は妻のもの」「妻は夫のもの」という日本語の表現は、極めて強い所有の意味を有しており、何か違和感があるのですが、フランスの実存主義哲学者ガブリエル・マルセルの主著『存在と所有』という場合や、「私には子供が3人いる」という英語表現のように、広い意味での「所有」を表わす概念は存在すると言えますので、「所有の排他性」という表現は、それほど語弊があるとは言えないでしょう。
いずれにしても、この「所有の排他性」は、言い換えれば、「それ以外のもの(人)をもっては取り替えることのできない価値」を有した存在だということです。それは前回も述べたように、「私にとって大切な人(存在)」というのは、それは「私にとっての存在そのものが価値を持っている、そのような存在」だということです。だからこそ、親や子や配偶者(夫や妻)という存在が、「かけがえのない価値」を持つと言えるのです。
★「思想新聞」2025年5月15日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「天安門事件から36年~日米同盟の危機」2025年 6月4日 中野駅