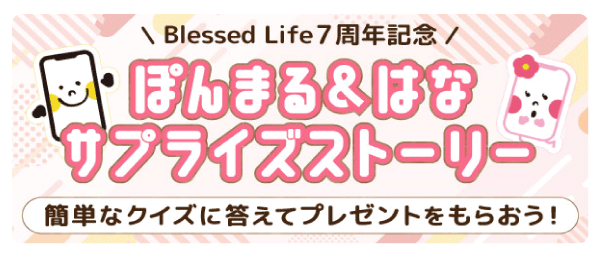レダ摂理 5
農業に向かない土壌に苦戦し、漁業にも着手
2025.04.16 17:00

レダ摂理 5
『世界家庭』に掲載された飯野貞夫さんの証しを、毎週水曜日配信(予定)でお届けします。
飯野絢子(あやこ)さんの証しに続き、絢子さんの夫であり、サウジアラビア国家メシヤとして活躍した飯野貞夫・天一国特別巡回師(777家庭)のレダでの歩みを紹介します。(一部、編集部が加筆・修正)

農業に向かない土壌に苦戦し、漁業にも着手
レダでは、農業を通して基盤ができないかと、自立に向けて懸命の努力が続きました。日常、必要なトマトやキュウリ、ナス、キャベツなどは細々と収穫できましたが、継続して担当する経験者がいませんでした。稲、大豆、ゴマ、ジャトロファ(中南米原産の落葉低木で、種子から採れるバイオ燃料が注目されている)など、収益を期待できる作物は、一時的に収穫はあっても、鳥害で2年目から全滅という事態に追い込まれ、頓挫しています。まだ諦めてはいませんが、ここは塩分が多い粘土質の土壌のため、それを生かせる作物の発見が願われています。
一般的には、この地域は牧場くらいしか使いようがないとされ、本格的に農業をやっている所は全くありません。レダから何十キロも離れた所に先住民(チャマココ族)の村が点在していて、数百人が住んでいますが、彼らは狩猟民族で、狩りや魚釣りをして暮らしています。農業といえば、せいぜい家の周りに、マンジョウカという芋やマンゴーの畑を作っている程度です。青年は狩りをするか、牧童に雇われるか、何百キロも離れた町に出稼ぎに行くかしかありません。
彼らの中には、レダに働きに来る人もいます。待遇が良いので、喜んで働いてくれます。そんな彼らは、レダで学んだことを基に、少しずつ農業にチャレンジし始めています。農業が定着すれば、それまでの肉中心の食習慣が変わります。それが彼らの健康や長寿につながるのではないかと期待しています。

こうした村には2000年から毎年、日本から国際協力青年奉仕隊を送って、「ために生きる精神」を実践しています。まず、地球の砂漠化を防止するために、村や学校で植林活動を継続して行ってきました。教育の重要性に鑑み、学校や教科書さえもまともになかった村に学校を建て、教材を提供し、支援してきました。これらの活動は、日本の青年たちにとっても良い勉強になりますが、何より現地住民が歓迎し、毎年首を長くして待ってくれているので、大きな意義を感じています。
2004年から、レダでは、中田実さん(ハンガリー国家メシヤ、777家庭)が所長となり、全責任を持って取り仕切ることになりました。彼も絶えず、レダの自立と同時に、国家に影響を与えていくためにはどんなプロジェクトがふさわしいか、真剣に祈り求め、熟慮してきました。
そうした中で、農業から水産にシフトし、魚の養殖に取り組むことになりました。中田所長と共に、上山貞和さん(スペイン国家メシヤ、777家庭)が先頭に立ち、トラクターを駆使して幾つもの池を造りました。そして、アスンシオン大学から、パクー稚魚5000匹を導入することになったのです。
2011年1月3日、同大学水産学部のマグノ教授と私たち夫婦は、アスンシオンからセスナ機で稚魚5000匹を携えてレダに向かいました。レダでは、中田所長が稚魚の到着を待ちわびていました。
ここからパクー養殖が本格的にスタートしました。それから2年後には早くもパクーの孵化に成功。そこで育った多くの稚魚をパラグアイ川に放流することで、乱獲で失われつつある本来の生態系回復に大きく貢献していくようになるのです。
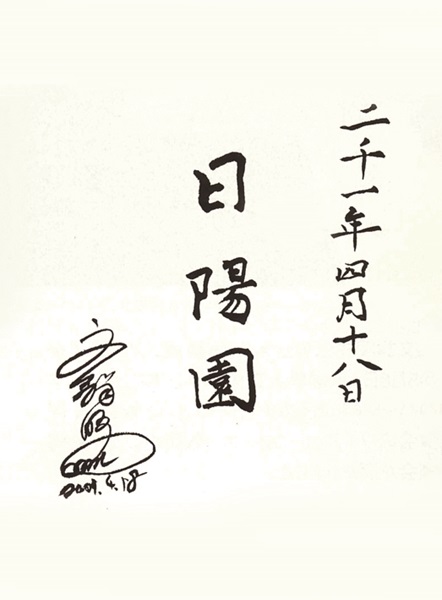
(続く)
---
次回は、「毎朝4時から1時間、『御旨と世界』を徹底訓読」をお届けします。