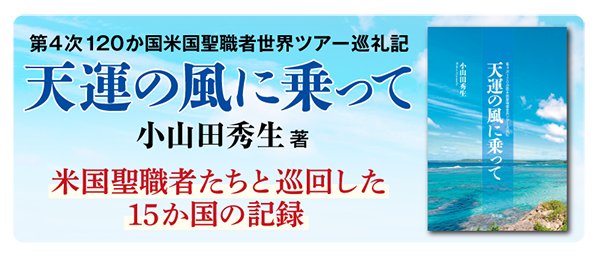愛の勝利者ヤコブ 29
石の枕
2023.04.10 12:00

愛の勝利者ヤコブ 29
アプリで読む光言社書籍シリーズとして「愛の勝利者ヤコブ」を毎週月曜日配信(予定)でお届けします。
どの聖書物語作者も解明し得なかったヤコブの生涯が、著者の豊かな聖書知識と想像力で、現代にも通じる人生の勝利パターンとしてリアルに再現されました。(一部、編集部が加筆・修正)
野村 健二・著
石の枕
ちょうど玉突きでもするように、言わず語らずのうちに相手に自分の思いどおりのことをさせてしまうリベカの舌を巻くような知恵。その土台の上に神の霊が温かく臨んで、ヤコブは神と家長イサクの公認のもとに、形こそ忍びの旅であったが、一人堂々と800キロにも及ぶ延々たる砂漠に挑んでいった。寂しいとも、恐ろしいとも思わなかった。それは男冥利(みょうり)に尽きる波瀾万丈(はらんばんじょう)の冒険の旅路であった。
かたやエサウも、父イサクがヤコブに「カナンの娘を妻にめとってはならない」と厳命してパダンアラムに送り出したことを聞いて、これまでの自分の軽薄な生活ぶりを反省した。そうして少しは孝行をして気に入られようという気持ちになり、例のイサクの異母兄イシマエルの娘で、長子ネバヨテの妹マハラテを新たに妻に迎えた。
さてヤコブが住み慣れたベエルシバを発ち、ハランへ向かう途中、ルズ(創世記28・19)という名の寂しい町はずれまでたどり着いた時、日がとっぷりと暮れた。懐は軽く、荒涼として石だけがごろごろと所くまなくころがっていた。
それがヤコブにはかえって爽快(そうかい)に思われた。手ごろな形のいい石を見つけると、それを枕に彼は、ごろっと大の字になって寝そべった。
やがて月が出、砂塵(さじん)がうずまいて走り抜けた。雲が自分の心と波長を合わせるかのように、右へ左へと揺れ動いている。その様子を見るともなしに見つめていたが、そのうち、1日足が棒になるまで歩きに歩いた旅の疲れがまぶたを重く押し、いつしかうとうとと眠りのうちに沈んでいった。
ふと気がつくと、地上から天に向かって頂がかすんで見えないような長い長いはしごがそそり立ち、その上を天使たちが上り下りしているのが見えた。神ヤハウェが自分のかたわらにあり、親しげに、「わたしはあなたの父アブラハムの神、イサクの神である」と語りかけるのをヤコブは夢うつつに聞いた。
あなたが伏している地を、あなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地のちりのように多くなって、西、東、北、南にひろがり、地の諸族はあなたと子孫とによって祝福をうけるであろう。わたしはあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。わたしは決してあなたを捨てず、あなたに語った事を行うであろう(創世記28・13〜15)。
その言葉はアブラハムに4度(創世記12・1〜3、15・1〜7、17・1〜5、22・15〜18)、イサクに1度(同26・24)、直接その前に現れてはっきりと契約されたものと全く同じ趣旨のものであった。ヤコブは驚いた。そうするだけの理由があったとはいえ、少なくとも父と兄をだまして、いわば略奪してきたともいえる祝福である。
もとより父イサクの祝福は、神ご自身の祝福と同じ権威を持つ動かすべからざるものではあった。しかし、それは正当な手段で得たものではないという心のわだかまりがあった。持ち前の楽天的な性格から、どうにかなるだろう、親がついていないだけかえって気楽だとさえ思い、過ぎたことをさして気に留めてはいなかったとはいうものの、このように改めて公然と、主ヤハウェご自身が我が身に臨んで、このように約束されようなどとは思ってもいなかったことだからである。
「主よ、それではわたしのあの行為を是認され、公式にアブラハムとイサクに臨まれたのと同様に、神の民の祖となるべき者として認められたのですか?」
答えはなかった。その代わり、天に向かってそそり立つはしごを上り下りする天使の姿が、はっきりと目の当たりにするように記憶に甦(よみがえ)ってくるのであった。
神はどんなにかヤコブに訳を説明してやりたいと思われたことだろう。しかしまだその時ではなかった。
そこで、母リベカのしたことが、そうしてあくまでも神の民の祖となりたいというヤコブの燃えるような執念がいかにすばらしいことか。そのことでどんなにご自分が喜ばれ頼もしく思っているか。そのことを示そうとされて、あえてヤコブの心に永遠に焼きついて消えない天のはしごと、天に至る道を守り続けている数知れない天使たちの、たとえようもない美しい幻をその言葉の代わりに見せてくださったのに相違ない。
今までのん気に、自分勝手な思いにばかりふけっていたヤコブにとって、しかしそれは晴天の霹靂(へきれき)にも等しい驚異であった。にわかに重い責任が自分の上にのしかかり、一夜に10年も歳を重ねたような気がした。
「もう自分はただの青年ヤコブではない。神の民の祖としてのヤコブなのだ」
自分に向かってそう言い聞かせると、ほとんど間髪を入れずに次の言葉が自分の口をついて出た。
「そして、この石ころだらけの暗黒の地を天にまでつなぐ、気のつき果てるほど重く、長く、苦しい忍耐のはしごをかけ渡す者として選ばれたヤコブなのだ」
そんな言葉はただの思いとしてさえ自分のうちにはなかった。それゆえそれは、自分の思いのうちに神がこれからの長い旅路への贈り物として注がれた言葉でなければならないはずだった。そうだ、その「重い」「長い」「苦しさ」──それこそ今までの自分に欠けていたものだった。それをこれから身に余る恩恵の代償として支払っていかなければならないと、ヤコブは決意した。
「これはなんという恐るべき所だろう。これは神の家である。これは天の門だ」(創世記28・17)と、ヤコブはつぶやいたと聖書にはある。
その「恐れ」──それはアブラハムがイサクをささげようと決意した時、またリベカが一身を滅ぼしてでもヤコブに祝福を受け継がせようとした時に感じた「恐れ」と同じものであったろう。100メートルもの高みから飛び降りようとする時にも似た──しかも、重い苦しみと涙と、いつ果てるとも知れない絶叫のすべてを背負った恐れを、今ヤコブは自分の一生の貴重な宝として受け継いだ。
自分はヤコブであると共にリベカでもあり、アブラハムでもあり、アダムとエバ以来の「人類」の苦しみ、神の嘆きと恨みの総体でもあった。その歴史の全体がにわかに自分の肩に乗ったのだ。重くなかろう道理はなかった。
「『祝福』とはこのようなものだったのか。ならばそれを引き受けよう、何度でも繰り返し」──ニーチェならばこう言ったかもしれない。こういう大きな重荷を課す、存在感にあふれた神と出会わなかったニーチェはあわれである。
次の朝ヤコブは早く起きて、枕としていた石を取り、柱として立てた。小さくとも、すでにそれは宇宙の全体に等しい長さと、重さと、苦しさとを備えていた。やがて自分はこの石そのものになり切る。そう心のうちで誓いつつ、その頂に自ら祝福の油を注いだ。
その石がやがて時至ればキリストとなり、神よりの油を受けてその右に座す者となる。──そういうことをヤコブは知る由もなかった。ただ自分のあらん限りの力をふりしぼって石たらんとしたのみである。
「ヤコブは誓いを立てて言った、『神がわたしと共にいまし、わたしの行くこの道でわたしを守り、食べるパンと着る着物を賜い、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主をわたしの神といたしましょう。またわたしが柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべての物の10分の1を、わたしは必ずあなたにささげます』」(創世記28・20〜22)。
その誓いを込めて、その場所をヤコブはベテル(神の家)と名づけた。
やがて燦々(さんさん)と輝く、今生まれたばかりのような朝の陽(ひ)を浴びつつ、ヤコブは悠然と限りない砂漠の地平線に向かって歩んでいった。その様子はこれまでのヤコブとどこも変わりがないように思われた。しかしそのひきしまった顔には、もはやそれまでのような甘さはなかった。1000年の重みをその額のしわに刻みつつ、しかも何事もなかったかのように泰然として歩んでいく。……
大したやつだ。この若さでこの広漠たる砂漠を何とも思ってはいない。わたしの思ったとおりの男にイサクとリベカよ、よくぞ育てあげてくれた。アブラハムとイサクが果たそうとして果たしえなかったすべてを、この男なら必ずやりおうせるであろう。
そういう神の声なき声が、大地の底から鳴り響いてくるようだった。
---
次回は、「かかとをつかむ者」をお届けします。