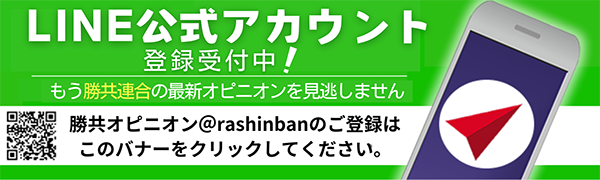共産主義の新しいカタチ 80
ポストモダン思想に共通するトーン
2025.09.24 17:00
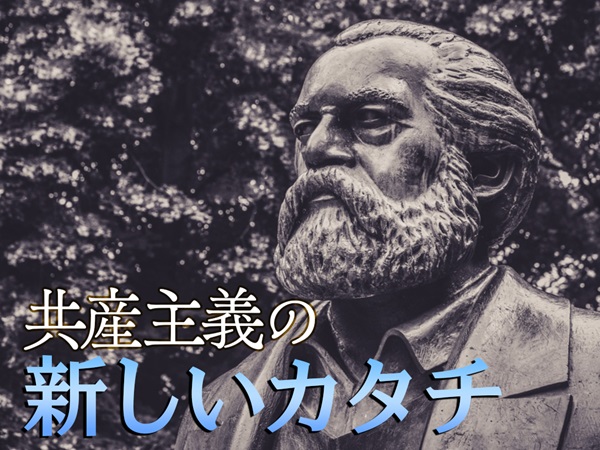
共産主義の新しいカタチ 80
現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?
国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)
反権力としての「ラングの専制」
ロラン・バルト(上)①

構造主義・ポスト構造主義・ポストモダンと称される思想群には、総じて「反西欧」「反コギト中心主義」などといった共通するトーンを帯びていることが分かります。
そしてそれは「個人的原子論」とも言うべきものに彫琢(ちょうたく)されて姿を現します。ロラン・バルトの「構造主義的記号論」も、その典型例と言えます。
ポストモダン思想に共通するトーン
この「共通のトーン」とは、「反西欧(=「反キリスト教」)」「反コギト(思惟する自我)=反形而上学」「反理性主義」で、これはどんな構造主義関係の入門書・参考書にも共通して強調される特徴です。
確かに、この「共通のトーン」にあるのは、人間個人の「決断」と「主体性」が特筆大書された「実存主義思想」の対極にあるものであることがうかがえます。
ここで考えたいのは、前回も触れた宗教をめぐる「二つの民主主義の流れ」の模式図で表わされた「差異」が現代にまで洋の東西を問わず、国家・社会に影響を及ぼす可能性です。
レヴィ=ストロースが否定したのは、あくまでサルトルのマルクス主義的実存主義であり、マルクスの考え自体の全否定ではなかったのです。このため、東洋的なマルクス主義(例えば毛沢東主義)が、ソ連主導マルクス主義(スターリニズム)に対し不満を抱く勢力の受け皿となりました。
その毛沢東流のマルクス主義(マオイズム)を信奉したのが、構造主義的マルクス主義者でフランス共産党員であったアルチュセールです。彼らにとってマルクス主義は「西欧」よりも、アジアやアフリカなどの「第三世界」で輝きを増す「真理」と映ったのです。
ところがその一方、マルクスの思想こそ実は「全体主義」(ファシズムと共産主義)へと帰結するイデオロギーと考えたのが、先に紹介した「二つの民主主義の流れ」を説く政治学者A・リンゼイでした。この考えに近いのが、実は宗教哲学者マルティン・ブーバーの「我と汝」の考え方です。
ポストモダンと個人的原子論の彫琢
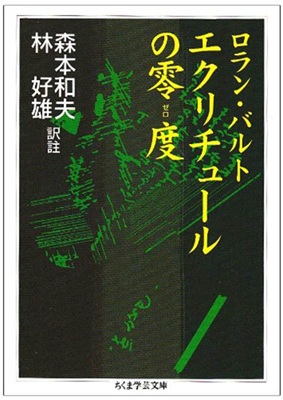
ロラン・バルトが主張する「ラング(母国語)の専制からの解放」というものは、コミュニケーションから形成される人間の絆を断ち切り、個々人に切り離してしまうことになりかねません。ましてや権力論を唱えるミシェル・フーコーの立場を援用するならば、「母国語」(ラング)は「権力によって恣意(しい)的に定められた。従ってそんな権力のルールに従う必要などない」と考えてしまいます。
かくして個々人が家族や社会から切り離されたいわば一種の「個人的原子論」というべきものが彫琢され正当化されて、それが個人主義的政策に反映していくことになります。
この「ラングの専制」に対してバルトの唱える「異論」とは、分かりやすい例として挙げれば、「日教組」教師らが唱える「日の丸・君が代の強制は憲法違反」という主張であったり、「入学式・卒業式は国家によるエリート意識植え付けの場であるからこれを粉砕しなければならない」という「入学式・卒業式粉砕闘争」の論理などです。
この「極左」の論理では、「国家機関という装置から自治を勝ち取って大学が存在している」という神話を根拠もなく一方的に信じているに過ぎないのです。だからそこには、自分の親が払った税金によって大学が運営されている、という視点が全くありません。
(続く)
★「思想新聞」2025年9月15日号より★
ウェブサイト掲載ページはコチラ
【勝共情報】
国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅