愛の知恵袋 200
一人暮らしの安全対策
2025.07.18 22:00
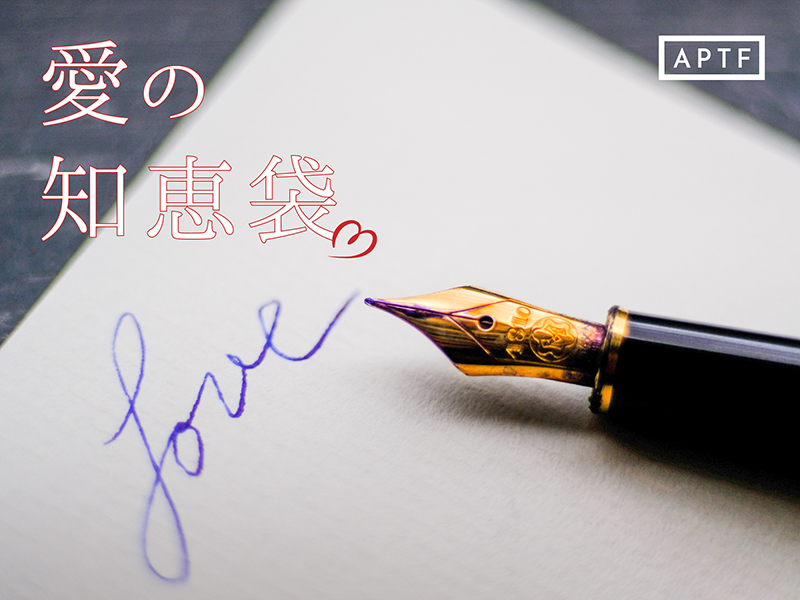
愛の知恵袋 200
一人暮らしの安全対策
松本 雄司(家庭問題トータルカウンセラー)
おかげさまで、「愛の知恵袋」も連載200回を迎えました。読者の皆様からいただく感想や激励の言葉が継続の力になっています。心からお礼申し上げます。
一人暮らしの男性が倒れた!
さて、今回のお話は、一人暮らしの中高年の方、そして、若い方でも親や祖父母が遠くで一人暮らしをしている場合には、ぜひ聞いておいてほしいことです。

先日、私がカウンセラーとして長年(ながねん)相談を受けていた70歳の男性が突然倒れました。彼は結婚して10年後に妻子と別居状態になり、25年後には離婚。子供たちとも連絡が取れない状態になって、天涯孤独のような身の上になってしまいました。
そして、人付き合いが苦手な性格のため、友人や親戚とも疎遠になってしまい、私と電話で話すたびに、「寂しい、寂しい」と言っていました。
「もう、先生しか安心して話せる人がいません」というので、私も仕事の範囲を超えて、できる限り時間を割いて彼の話を聞いてあげました。
彼は他県在住なので、私が一番心配したのは事故や急病の時の対処でした。そのため、「地元の市役所に行って相談し、民生委員とも話をしておくように」とアドバイスし、また、体調が急変した時のために、即対応してくれるサービスの活用も勧めました。
それで彼は、A社の「みまもりサポート」を契約していましたが、今回はそれが役に立ちました。彼が脳疾患で急に体調が悪くなって倒れた時、A社のガードマンが駆け付けてくれ、救急車を手配し、病院に搬送してくれたのです。
もし、「みまもりサポート」の助けがなければ、倒れても誰も分からず、孤独死となり、発見されるのもずっと遅くなっていただろうと思われます。
万一のための対策をしておこう
私自身も妻が他界した後の7年間ほどは一人暮らしでした。もし、脳疾患や心臓疾患で突然動けなくなった時にはどうするかを考えなければなりませんでした。
当時、子供たちは遠隔地にいたので、私が倒れても駆けつけることはできません。
幸い、私の姉夫婦が同じ市内の車で15分のところに暮らしていたので、緊急の場合は姉に電話をして対処してもらうようにお願いし、私の自宅の合鍵も預けました。
理由は、もし駆け付けてくれたとしても“鍵”がなければ入れないからです。
脳卒中や心筋梗塞の場合は、数分の時間差が生死を分け、また、後遺症の程度にも大きく影響します。
警備保障会社の見守りサービス活用も考えよう
一人暮らしの方には、大手の警備保障会社が運営している中高年者のための“見守りサービス”を活用することをお勧めします。
私もいくつかの会社のサービスを調べてみましたが、非常に有効だと思います。
具体例を挙げると、A社の「みまもりサポート」では、自宅のリビングなどに、コントローラー器を設置してくれます。体調が気になる時は“相談ボタン”を押せば、24時間常駐の看護師さんに相談することができます。
また、“緊急ボタン”を押せば、ガードマンが駆けつけて、必要に応じて救急車を呼んでくれます。さらに、火事や強盗などの場合は消防署や警察に通報してくれます。
オプションとしては、首にかけるペンダント型の緊急ボタンも利用できます。これは家の中のどこで倒れてもその場でボタンを押せば駆けつけてくれるサービスです。
他にも、日々の安否確認、センサー感知、火災・ガス漏れ感知、外出時の位置情報取得、熱中症見守り、災害時の避難支援、外出・帰宅のお知らせ・・・等のオプション機能を追加することもできます。
また、S社の「見守りサービス」の場合は、次のような備えができます。
①安否見守りサービス・・・廊下やトイレなどにセンサーを設置し、一定時間動きがなければ異常信号が送られ、会社が確認。必要なら駆けつける。
②救急通報サービス・・・緊急時、ペンダント型の「マイドクター」を握るだけで、救急信号が発信され、救急対処員が駆けつける。また、空き巣対策、火災通報、押し売り対策も非常ボタンで対処できる。
③電話相談・・・体調に心配があれば、24時間いつでも看護師に電話相談できる。
以上、具体例として代表的な2社の見守りサービスを挙げてみました。他にも、一人暮らしの親の見守りのためのグッズはいろいろあるので、ネットで調べてみるとよいと思います。
人生の最後を、愛する家族に見守られずに他界するのは悲しいことです。
また、子供としても、苦労して自分を育ててくれた親の最期を看取ってあげられなかったとしたら、生涯の悔いとなるでしょう。
地上人生は有限であり、親と子にもいつかは“今生(こんじょう)の別れ”が来ることは避けられませんが、人間として“衷心の情を尽くすべき瞬間(とき)”というものがあると思います。
親のためにも、子のためにも、万一の時のための備えはしておきたいものです。


