日本17宗教人の横顔 4
内村鑑三(下)
2024.02.08 22:00
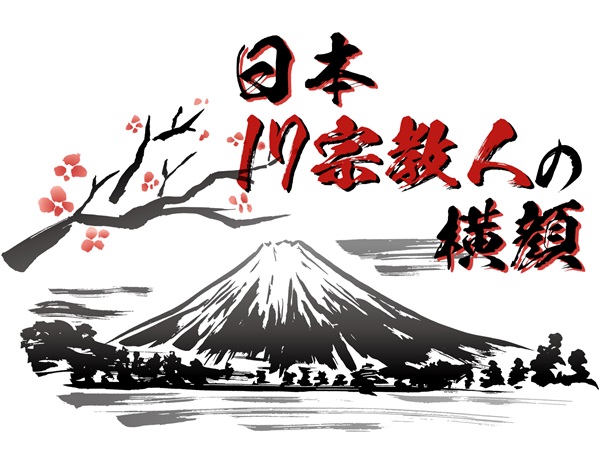
内村鑑三(下)
『中和新聞』で連載した「日本17宗教人の横顔」を毎週木曜日配信(予定)でお届けします。
日本の代表的な宗教指導者たちのプロフィル、教義の内容、現代に及ぼす影響などについて分かりやすく解説します。
再臨運動を展開
二つの「J」にささげる
1884年(明治17年)、23歳で米国に渡った内村鑑三は、フィラデルフィア郊外にあるエルウィン白痴院という所に落ち着き22人の子供の世話に当たった。彼はかねてから慈善事業に興味を持ち、実践的な愛こそキリスト教の本質だと考えていたからである。しかし、苦労の毎日の中で鑑三は、「私は自分を犠牲にして子供たちに尽くしているが、この思いは自分の心を救おうとする利己的な考えから来ているのではないか」と苦悶(くもん)し、子供たちに慕われながらも、やがて「自分を捨て、本当に神に仕える道を発見するために」、この白痴院を去ることになる。
そして鑑三は、クラーク先生の母校でもあるニューイングランド州のアーモスト大学に入学。ここで25歳から28歳までの足かけ3年間を苦学のうちに過ごすのだが、シーリー学長との出会いは、信仰の一大転換を与えてくれた。鑑三が「私は白痴院の看護人もつとめて、人のために尽くし、毎日の行いも神のみ心に沿うようにしてきました。他の人は私をほめてもくれますが、私の心の奥には、喜びも満足もないのです」と、心の悩みを訴えた時、シーリー学長は、慈しみのまなざしで静かに言われた。
「あなたは、心の内側ばかり見ているようだ。今度は、あなたの心の外側をご覧なさい。あなたは、ちょうど子供が植木を鉢に植えてから、それが成長しているかどうかをたしかめるために、毎日その植木を引き抜いてみるようなことをしているのです。そんなあせったやり方ではいけません。なぜ、神と日光にまかせて信頼し、安心して自分の成長を待たないのですか。どうして、自分を省みることだけに心をつかって、十字架の上に罪をあがなって下さったイエス・キリストを、黙って仰ぎみないのですか」
鑑三は、シーリー学長の全人格を通して指し示された福音信仰によって、これまで苦しんできた我執や魂の聖潔の問題が正しく解決されたと確信。やがて彼は、あらためて信仰の道に生きるために日本へ帰ることにした。

明治政府は、早く西洋に追いつこうと、西洋文明の中から、機械や技術、社会の制度といったものだけを急いで取り入れ、一方では、「富国強兵」のもと、一日も早く独立国として力のある国にしようとしていた。したがって、西洋文明を支えていた精神的なもの——民主主義、自由・平等、キリスト教の教えなどは国の政策の邪魔になるとして、取り除こうとした。このような時代に、アメリカで真の信仰を得て帰国した鑑三は、「今の政府の考えでは日本は滅びてしまう。なんとかしてキリストの教えを広めて日本を救わねばならない」と考えた。これこそ、彼の考える「愛国心」であり、これからの自分の生涯を「二つのJ(イエスと日本)にささげよう」と決心するのである。
鑑三は第一高等学校(今の東大教養学部)をはじめ、新潟、大阪、名古屋、東京で教師、新聞記者、雑誌主筆を経た後、1900年(明治33年)からは、個人雑誌「聖書之研究」の発行に力を注いだ。この雑誌は彼が亡くなるまで毎月発行し続け、375号までになった。また、「基督教徒の慰め」「余は如何にして基督信徒となりし乎」「後世への最大遺物」など、貧しい暮らしの中で多数の書物を著し、さらに日露戦争反対論、社会・文明批判などの論陣を張り、国や社会に働きかけた。
また1900年ごろから、いわゆる無教会主義を展開、独立伝道者として立つとともに、自宅で聖書講義や集会、礼拝を持ち、多くの人たちが集ってきた。1918年1月には、「聖書の預言的研究講演会」を青年会館で開き、以後毎月各地で再臨運動を展開した。北海道から岡山に至るまで熱狂的な信仰復興と教会革新の意欲が生まれ、キリスト教界に大きな波紋を投げかけた。救い主キリストが、罪と腐敗に満ちた現実の教会と世界を正しく処理したもうことを宣言することが彼の再臨信仰であった。
1930年(昭和5年)に入ると、発作的な心臓衰弱がしばしば襲い、ついに3月28日、70歳で神に召されていった。彼は最後まで、日本のため人類のために福音を伝えること、何人をも赦しその代わりに自らの罪も赦してもらうこと、そして日本武士として潔い生涯を送ることを願った。多磨霊園(東京都府中市)の墓碑には、今も次の言葉が刻まれている。
「余は日本国のために 日本国は世界のために 世界はキリストのために そして、すべては神のために」
---
次回は、「聖徳太子」をお届けします。



