日本人のこころ 7
インド~遠藤周作(4)『深い河』
2018.08.13 22:00
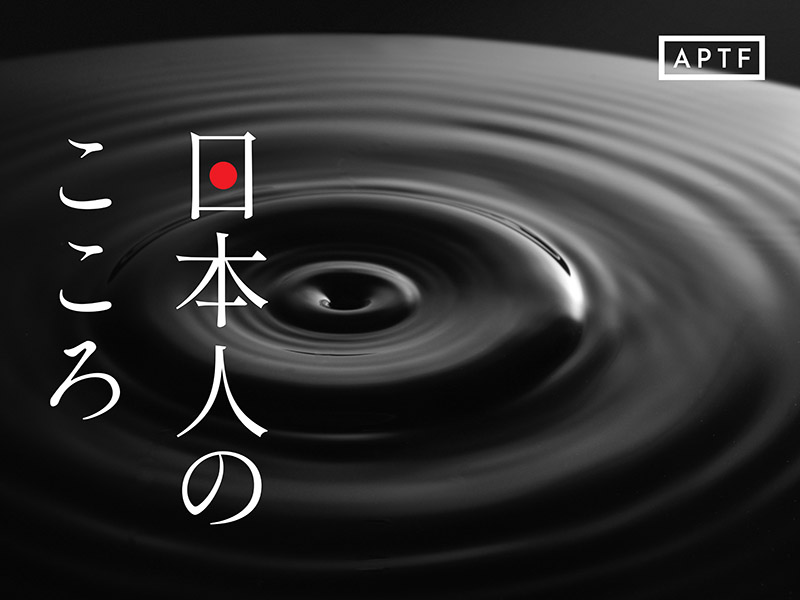
日本人のこころ 7
インド~遠藤周作(4)『深い河』
最後の長編小説
『深い河』は1993年に発表された遠藤周作70歳の長編小説です。遠藤は96年に亡くなるので、生涯のテーマである「キリスト教と日本人」の最後の作品となりました。黒人霊歌の「深い河」(ディープリバー)はイスラエルにあるイエス・キリストが洗礼を受けたヨルダン川のことで、表題としては、日本とヨーロッパとの宗教や文化の「深い隔たり」を暗示しています。
物語は、戦後40年の日本から、それぞれの業を背負う5人がヒンズー教の聖地、インド・ベナレス(ヴァーラーナシー)へのツアーに参加し、いろいろ体験する形で展開します。
美津子は学生時代に不器用で純朴な大津を誘惑し、捨てます。大津はフランスの神学校に留学し、美津子は愛のない結婚をします。美津子は新婚旅行先で修道院にいる大津を訪ねますが、美津子に捨てられて初めて神の召命を聞いたと告白する大津に戸惑います。帰国後、美津子は離婚し、病院のボランティアで「愛のまねごと」を始め、大津がベナレスの修道院にいると聞き、ツアーを申し込みます。
磯辺はがんを患った妻が、死の直前に残した言葉「必ず生まれ変わるから、私を探して」の意味を探り、ベナレス郊外の村に住む前世の記憶を持つ少女が妻なのではと思い、ツアーに参加します。妻の看護をしていた美津子とは顔見知りでした。
童話作家の沼田は、自分が手術を受けている時に死んだ九官鳥を、自分の身代わりになってくれたと信じています。木口はビルマ戦線で死線をさまよった人で、死んだ戦友の肉を食べたことから、罪の意識に苦しんでいます。そして、戦友の慰霊をしようとツアーに参加します。添乗員の江波は、ヒンズー寺院に客を案内し、病気に苦しみながら人間に乳を与え続けるチャームンダー女神を紹介するなど、インドの宗教に通じています。
「さまざまな宗教があるが、それらは皆同一の地点に集まり、通じる様々な道である」という考えの大津は、キリスト教の教官から異端とみなされて、神学校や修道院を追放され、最後にたどり着いたベナレスの教会で奉仕活動をしますが、路上の死体をガンジス河に運んだことで追い出され、ヒンズー教の道場に身を寄せていました。
ツアー客はそれぞれの思いをインドに投影して、自分の旅をします。
磯辺は郊外を探し回りますが、妻の生まれ代わりの少女には会えません。沼田は店で九官鳥を買い、かつての身代わりのお礼として、空に放してやります。木口は急病で倒れますが、美津子に助けられ、ガンジス河に向かい慰霊の経を読みます。大津と再会した美津子は、彼の無償の行為の底に何かがあるのを感じます。
折しもインディラ・ガンジーが暗殺される事件が起き、世情が騒然としてきます。ツアー客の一人が、火葬に付される遺体を撮影しようとして参列者の怒りを買い、彼をかばった大津は大怪我を負います。そして帰国の直前、美津子は大津の死を知らされました。
ヨブ記を書きたい
「この小説が私の代表作になるかどうか、自信が薄くなってきた。しかし、この小説のなかには私の大部分が挿入されていることは確かだ」と「『深い河』創作日記」に記したように、宗教多元主義や汎神論、輪廻転生、前世記憶など遠藤の多彩な問題意識が盛り込まれているのが本書です。もっとも遠藤の作風は、断定的な結論を示すのではなく、いろいろな事例を出しながら、読者が自分で考え、深めるのを期待し、促すものです。
その後、遠藤は93年5月に腹膜透析の手術を行い、一時は危篤状態に陥りますが、奇跡的に回復します。入院中、苦痛に耐え切れず、愚痴や泣き言を繰り返していましたが、順子夫人に「ヨブ記の評論を書くのでしょう」と励まされ、決心してからは自分をヨブの境遇に重ね合わせ、愚痴を言わなくなったそうです。
旧約聖書のヨブ記のテーマは、「罪のない私を神はなぜ苦しめるのか」です。
ヨブは高潔な人で、7人の息子と3人の娘、そして多くの財産を持っていました。天で神がサタンにヨブの義を示すと、サタンもそれを否定することはできません。しかし、サタンはヨブの信仰の動機を怪しみ、財産を失えば神を呪うだろうと指摘します。
ヨブを信頼する神は、サタンが彼の財産を奪うことを認めます。サタンによってヨブは最愛の者や財産を失いますが、信仰を失うことはなく、サタンは敗北します。次にサタンはヨブをひどい皮膚病にかからせます。当時の社会では、皮膚病は社会的な死を意味していました。ヨブの妻さえ「神を呪って死ぬ方がましだ」と言いますが、ヨブは「わたしたちは、神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないか」と答えます。
ヨブの言葉としては、「わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う」がよく知られています。つまり、創造主である神との関係が最も重要であるとの考えで、紆余曲折しながらも、それを貫いたヨブは、最後に失ったものすべてを回復し、平安な死を迎えます。
残念ながら、遠藤はヨブ記を書くことなく亡くなりましたが、その生涯を通してヨブ記を生きたように思えます。



