日本人のこころ 3
宮城~遠藤周作(2)『侍』
2018.07.16 22:00
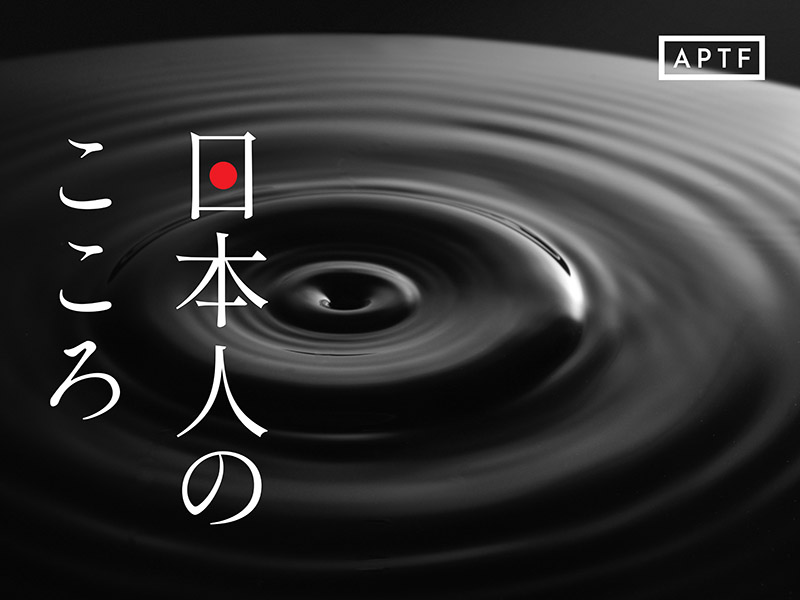
日本人のこころ 3
宮城~遠藤周作(2)『侍』
ジャーナリスト 高嶋 久
支倉常長をモデルに
1966年に小説『沈黙』を発表した43歳の遠藤周作は、母のようにやさしい神、貧しい人々と共に歩み、命さえ捨てるイエス像を求めて、『死海のほとり』『イエスの生涯』『キリストの誕生』の三部作を書き、57歳の1980年に歴史小説『侍』を発表します。

主人公のモデルは伊達藩の鉄砲隊に所属し、小さな領地を持っていた支倉常長です。江戸時代初期、スペインとの通商関係を築けという主君伊達政宗の命を受け、スペイン人の宣教師ベラスコを副使に、商人ら一行180人を率い、石巻で建造されたガレオン船サン・ファン・バウティスタ号で1613年に出港し、メキシコ、スペイン、ローマをめぐる長い旅をします。
太平洋を越えメキシコに至り、スペインの総督に会いますが、本国まで行かないと交渉できないとなり、さらにスペインの船で、大西洋を越えて、スペインに着き、1615年に王フェリペ三世に拝謁します。遠藤は当初『王に会った男』という題を考えていました。
しかし、スペインで侍は、予想外の事態に遭遇します。1612年と13年にキリスト教禁教令を出した江戸幕府による迫害の激化が日本から報告されていて、それがスペインとの交渉を難しくしたのです。支倉らは案内役の宣教師から、交渉を有利に進めるために洗礼を受けるよう求められます。
『侍』には主人公が不安を抱きながら、役目のためにと洗礼を受ける一節があります。
「(形だけのことだ)侍は祈るかわりにまたおのれに言いきかせた。(俺はあのみじめな男なぞ拝む気にはなれぬ)…(俺はなにも信じておらぬ)…なぜこの痩せこけ、両手を釘づけにされた男にむきになるのか、侍は自分でもふしぎだった。もし本当に形だけのことならば、このように心に繰りかえし同じ言葉を言いきかせる必要はなかった。胃液のようににがい感情がこみあげてくる筈もなかった」
侍は、形だけだと洗礼を受けるのですが、受けてみると不思議な気持ちになり、非常に大切なことをしたのだと感じ、痩せこけたイエスが、大きな力で自分に迫ってきたのです。
後に遠藤は「自分の意志で洗礼を受けたわけではないぼくは、支倉を書くことで、受洗の動機やその後の心理にぼく自身を投影できると思った」と語っています。父と離婚した悲しみからカトリック信徒になった母を喜ばせたい一心で、11歳の遠藤は洗礼を受けていたのです。
共に歩むイエス
侍は1620年に帰国しますが、心ならずも受けた洗礼のために迫害されるようになります。藩もキリスト教禁教に転じていて、冷たくあしらわれた侍は藩に裏切られたと感じます。この時、初めて侍はイエスとイエスを信じる人たちを理解し、信仰に心が開かれるのです。
小説では、侍に仕えていた与蔵も信仰を持つようになっています。侍が切腹を命じられた、最後の場面を引用しましょう。
「『ここからは……あの方がお供されます』突然、背後で与蔵の引きしぼるような声が聞こえた。『ここからは……あの方が、お仕えなされます』侍はたちどまり、ふりかえって大きくうなずいた。そして黒光りするつめたい廊下を、彼の旅の終りに向って進んでいった」
遠藤に導かれるように洗礼を受けた精神科医で作家の加賀乙彦は、「遠藤さんは、侍は私の分身、私自身なんだよと言っていた。誰もがああいう弱さを持っている。しかし、弱い人間だからこそ、弱いイエスに仕えることが大きな喜びになると言った」と語っています。
それぞれの信仰
『沈黙』がフィクションが多いのに比べ、『侍』は史実に誠実に書かれています。宣教師ベラスコはスペインとの通商を成功させることで、対抗する修道士会を出し抜き、自分が日本宣教の責任者になることをもくろみます。実際、そんなしたたかな人物だったようです。

失意のベラスコはマニラに帰るのですが、そこから再度日本に密航し、捕らえられます。しかし、『沈黙』の転んだ宣教師ロドリゴとは違い、強い信仰を示して殉教します。これも事実で、そうした信仰もあることを、遠藤は描いているのです。
遠藤が当初考えていた『王に会った男』という題の王とは、1人はスペインの国王であり、もう1人は「人々から軽蔑され、拒まれ」てきたみじめな王イエスです。そして、遠藤は、そんなイエスになら一緒にいてほしいと思うのです。
加賀乙彦は、カトリック教徒の死刑囚との文通を基に小説『宣告』を書きますが、遠藤から、「無免許運転をしている」と言われ、泊まり込みで神父の話を聞き、やがて遠藤の付き添いで聖イグナチオ教会で洗礼を受けます。
加賀が死刑囚の話をすると、遠藤は「死刑囚の信仰は神にすがるという思いがあるだろう。そういう信仰は本当の信仰ではない。ほんわかとした喜びが信仰の世界にはある」と言ったそうです。祈りと共にユーモアの作家だった遠藤をほうふつさせる言葉です。

