日本人のこころ 68
紀貫之『土佐日記』
2022.11.06 17:00
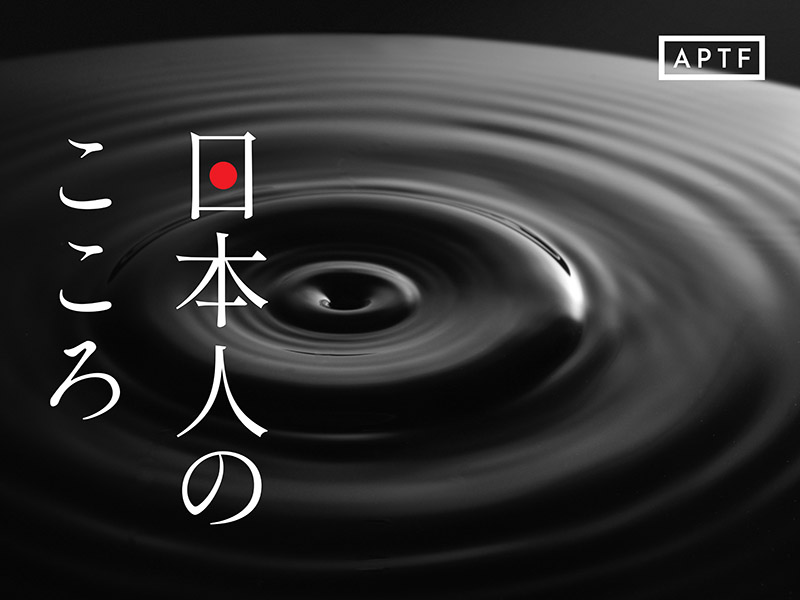
日本人のこころ 68
紀貫之『土佐日記』
ジャーナリスト 高嶋 久
女もしてみむとて
「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり」との書き出しの『土佐日記』は、平安時代に成立した日本初の日記文学です。著者は『古今和歌集』の選者でもあった歌人の紀貫之で、930年から934年まで土佐国の国司を務めており、任期が終わって京に帰る旅程の55日を綴っています。内容の中心は土佐国で亡くなった愛娘への思いと、早く帰りたい京への気持ちで、57首の和歌が含まれています。
当時、男性の日記は漢文で書かれていましたから、元は漢文のものを、帰京後、創作を交え紀行文風に仮名で書いたものとされています。『土佐日記』の影響は大きく、特に女性作家による『蜻蛉日記』や『和泉式部日記』『紫式部日記』『更級日記』などが生まれるきっかけになりました。漢文は中国文化の模倣ですが、遣唐使が中止になり、国風文化と呼ばれる日本独自の文化様式が生まれていた時代のことです。
中国の行政は科挙の試験を通った官僚たちが担っていたのですが、律令制を取り入れながら科挙は導入しなかった日本では、貴族の家業として実務を担当するようになります。そこで、親から子へと仕事を伝える必要があり、それが漢文の日記となったのです。
中国の官僚の条件は漢文が正確に書け、漢詩で自分の気持ちが表現できることで、後者が日本では和歌になります。官僚も人間社会なので、気持ちが通じ合わないといい仕事はできません。ですから、漢文で業務をこなしながら、和歌で心の交流をしていたのです。

娘を亡くした悲しみ
『土佐日記』は12月21日、土佐の国府を船で出発するところから始まり、土佐の大津に1週間逗留してから、浦戸、大湊、宇多の松原、奈半の泊、羽根、室津と渡り、1月29日に阿波の土佐泊浦に到着します。その翌日、鳴門海峡を渡り、本州に向かうのですが、当時は戦乱の真っただ中で、海賊に襲われないよう真っ暗な夜中にこっそり航海し、淡路島の沼島(ぬしま)を経由して大坂の和泉の灘に無事に到着します。
ようやく帰り着いた京の屋敷が荒れ果て、家を預けていた人の心も荒んでいたのですが、庭に松が新しく生えているのを見つけました。そこで詠んだ歌が「うまれしもかへらぬものを我がやどに 小松のあるを見るがかなしさ」(生まれても帰ってこない子供を思うと、ここにある小松を見ることが悲しい)と、「見し人の松のちとせに見ましかば とほくかなしきわかれせましや」(亡くなったあの子を松のように千年見ることができたのなら、こんな悲しい思いはしなかったのに)です。
懐かしいわが家に着いても、かわいい娘はもう帰ってこない。「わすれがたくくちをしきことおほかれどえつくさず。とまれかくまれ疾くやりてむ」(忘れがたいことは書き尽くせないから、今この日記を破り捨ててしまおう)と書いて『土佐日記』を閉じます。
あるかなきかの世に
貫之の代表的な和歌を紹介しましょう。
「桜花散りぬる風のなごりには 水なき空に波ぞたちける」(桜の花を吹き散らした風の名残には、水がないはずの空に波が立っているようだなあ)
「吉野河岩波高くゆく水の はやくぞ人を思ひそめてし」(岩を打つ波が高く流れていく吉野川の水のように、あの人に思いを寄せるようになってしまった)
人を思う気持ちの強さを吉野川の激しい水にたとえています。
貫之の人となりがよく分かるのが次の和歌です。
「人はいさ心も知らずふるさとは 花ぞ昔の香に匂ひける」(人の心はよくわかりませんが、ふるさとの花の匂いはいつまでも変わらないものです)
京に帰った貫之が、昔よく使っていた宿に顔を出したときに、皮肉を言われてしまいます。その時に自分の気持ちは変わらないよ、という意味を込めて返した歌で、花に託して自分は昔のままだよと伝えています。
辞世の句とされるのが「手に結ぶ水に宿れる月影の あるかなきかの世にこそありけれ」(手ですくった水に映る月のように、あるのかないのかわからないような世の中だったのだなあ)
人生のはかなさを詠ったようにも見えますが、生まれてきた自然に帰っていくのだという、悟りの境地のようにも思えます。
945年に亡くなった貫之の墓は比叡山中腹の裳立山、坂本ケーブルの「もたて山駅」から300メートルのところにあります。



