日本人のこころ 53
松本健一『天国はいらない ふるさとがほしい』
2021.08.08 17:00
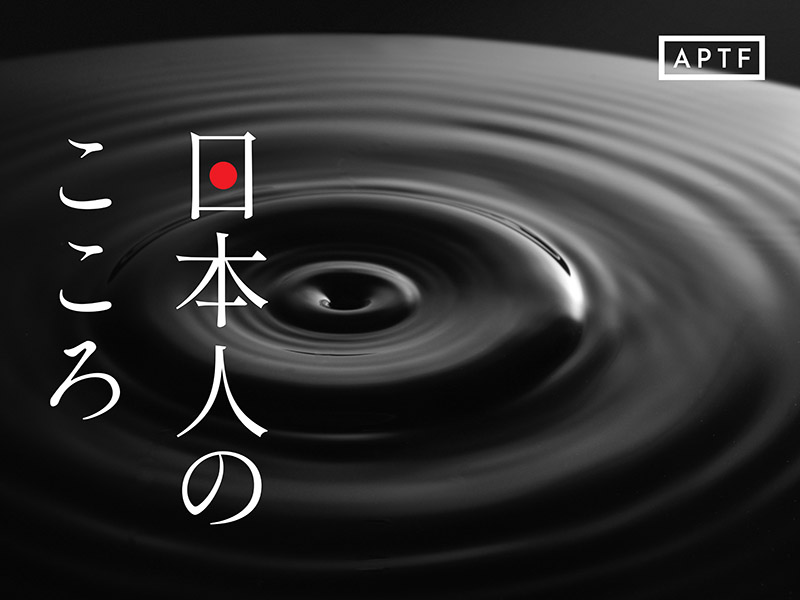
日本人のこころ 53
松本健一『天国はいらない ふるさとがほしい』
ジャーナリスト 高嶋 久
国よりも「パトリ」
松本健一さんは私より2歳年上の1946年、群馬県の生まれ。近くに米軍基地があったので、「占領下の日本」を肌で感じながら育ったそうです。東京大学経済学部を卒業し、旭硝子に入社、1年で退職し、法政大学大学院で近代日本文学を学び、1971年に出した評伝『若き北一輝』で注目され、以後、評論家、歴史家として執筆活動を始めました。
私は月刊雑誌「知識」の編集部員として何度か松本さんに執筆や対談をお願いし、年齢が近いせいもあって親しくお付き合いしました。北一輝の本を出して、「左翼からは右翼、右翼からは左翼と思われている」と苦笑していたのを覚えています。司馬遼太郎賞を受賞した『評伝北一輝』全5巻を岩波書店から出した時は、「ついに岩波がぼくの本を出すようになったんだね」と感慨深げでした。2014年にがんのため68歳で逝去、日本は惜しい人を失いました。
「知識」で片野次雄さんの「李朝滅亡」を連載するに際し、それを補足するようなものとして、日本の近代史や日韓関係に詳しい人と松本さんとの対談を連載しました。筆一本で生きてきた松本さんですが、1994年に麗澤大学経済学部教授になり、柏市にあるキャンパスをよく訪ねました。後には市民向けの講座も担当するようになり、教える喜びを感じているようでした。
民主党政権で菅直人内閣の時に内閣官房参与(東アジア外交問題担当)を務めたのは、仙谷由人内閣官房長官と大学時代からの友人だったからで、民主党議員に日本近代史を講義していました。
安倍晋三内閣での教育基本法改正の際には、文言について政府与党に相談され、「第二条(教育の目標)の『我が国を愛する……態度を養う』に『郷土』を入れるよう進言し『我が国と郷土を愛する』となった」と話していました。「国民にとって国家は抽象的だが、美しい風景やその人々は育ってきた郷土に育まれる。美しい国の根底、民族の生きるかたちがそこで生まれた」という、「パトリ(郷土)」への思いからです。
松本さんが目指したのは日本人の「ナショナル・アイデンティティ」の再構築で、思想的立場はリベラル・ナショナリストとされています。多くの著作の中で、取り上げたいのは『天国はいらない ふるさとがほしい』(人間と歴史社)です。
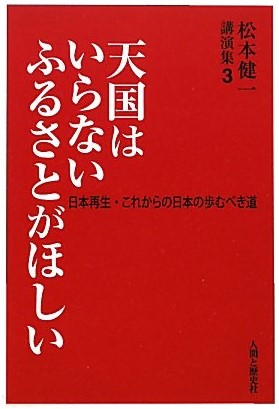
「天国はいらない、ふるさとがほしい」という詩を残したのは、ロシア革命に批判的だった詩人セルゲイ・エセーニン(1895~1925)です。チェルノブイリの原発事故で汚染され、移住が命じられたウクライナのナージャ村に住み続けている少数の人たちが、退去を勧告しに来た人に「なぜこの村に住み続けるのか」と聞かれ、エセーニンのその詩を暗唱したそうです。
松本さんは「これこそパトリオティズム(愛郷心)だ」とし、近代国家の「市民社会」は絵に描いたモチにすぎないと言っていました。私が母の介護を機に48歳で故郷に帰り、地域の集団営農に参加しながら、自治会など地域活動にいそしんでいると話すと、喜んでくれました。
アジアは「泥の文明」
松本さんのもう一つの関心は、グローバル時代の「文明の衝突」をどう乗り越えるかでした。そこで、ヨーロッパ、イスラム、アジアの文明を、それぞれ「石の文明」「砂の文明」「泥の文明」と名づけ、それらの本質を「外に進出する力」「ネットワークする力」「内に蓄積する力」ととらえる発想を提案したのです。私は農業をしていることから、泥の文明というのが素直に理解できました。
「アジアの泥の文明は、土地がすべての物を生んでくれるので、家や土地、共同体を守り、その内に蓄積する力が文明の本質になった。イスラムの砂の文明は、オアシスなどに拠点を作り、商業や情報のネットワークと物資を運ぶキャラバン交易によって利潤を生んだ。ヨーロッパの石の文明は土地が貧しいので、富を求めて外に出ていかざるを得ない。相手の文明を理解することができれば、そこに合う形で民主主義を根づかせる発想が生まれてこよう」というのが松本さんの考えでした。
私の妻は長野県駒ヶ根市の生まれで、市営住宅に中国の人民服姿の人が多くいたのに驚いたことがあります。残留孤児の人たちで、山崎豊子の『大地の子』のモデルになったのは南信濃です。
長野県の南部・伊那谷には明治に地方自治の表彰を受けた村や町が多くありますが、政府の政策に忠実であったため、日清、日露、太平洋戦争で大量の戦死者を出し、無理な満州開拓にも積極的に応募した結果、多くの残留孤児を生んでしまいました。
松本さんにその話をしたところ、満州開拓を疑問視し、分村・移民に抵抗した旧大下条(おおしもじょう・今の阿南町)村長・佐々木忠綱を教えてくれました。満州を視察した佐々木村長は、「持ち主のいない土地だと言われたが、人は住んでいるのでそうではない。広大だが、やせた土地だ」と感じ、悩んだ末、妻に「自分の子供だったら満州へ送るの?」と言われ、国策の開拓には参加せず、村民の力を高校と病院の建設に向けたのです。息子さんによると、佐々木村長は「常に教育と医療が人間にとって一番大事だ」と考えていたそうです。
農業や地域活動をしながら、松本さんの語る「パトリ」を懐かしく思い出しています。


